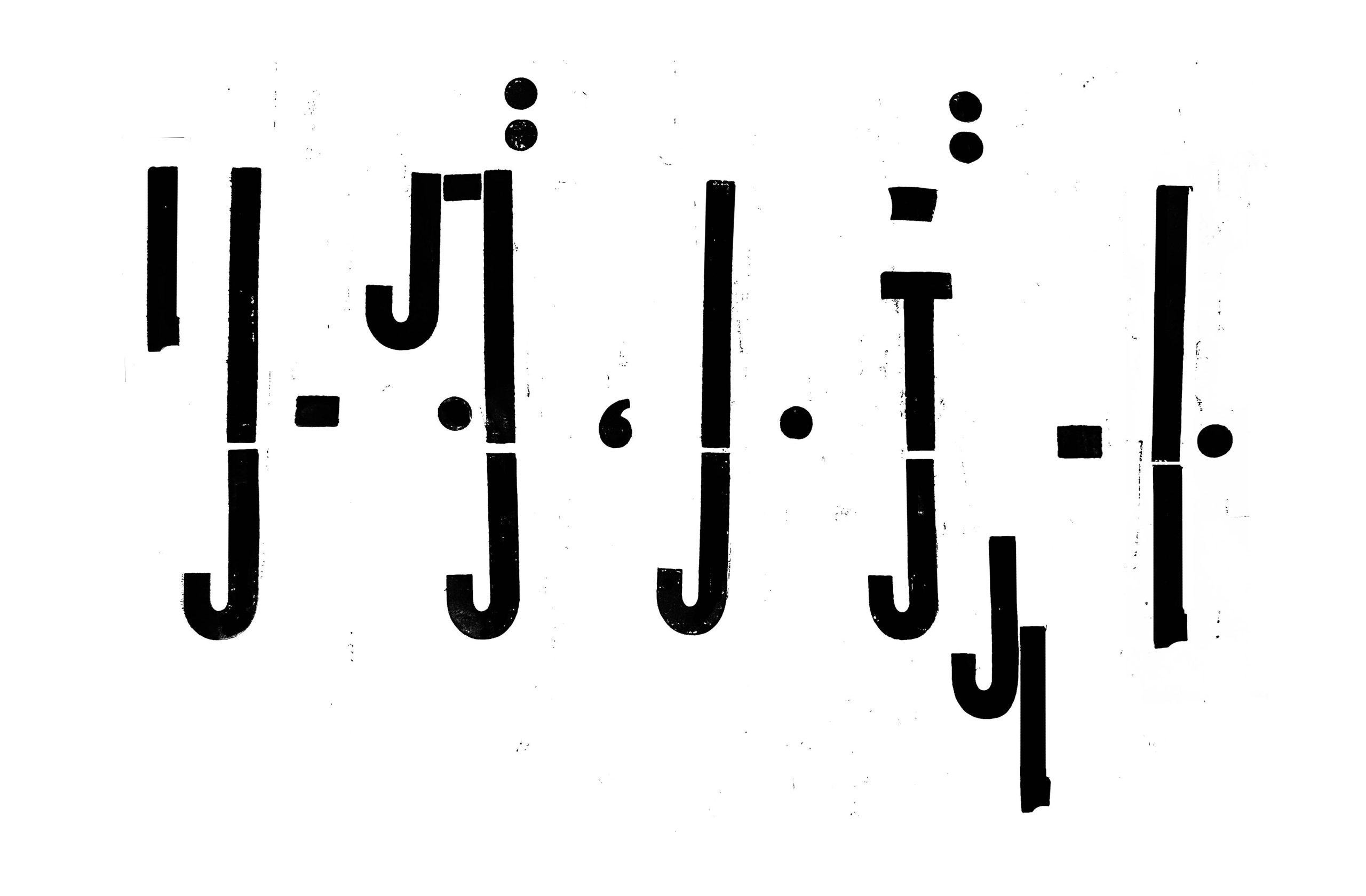THANK YOU
チェーン書店が街から消えていく

そう聞いて憤る方も多いかもしれないが、個人的にはそう考えている。その流れは人口の少ない地域から徐々に都市部へと広がっていく。地場で頑張る中規模のチェーン書店は本屋であることを諦め、全国チェーンの大型書店も採算の取れなくなった地方都市から順に撤退をはじめる。その一方でポツポツと増えていくのは「独立系書店」と呼ばれる個人経営の本屋で、全国的に見てもここ最近、実際に増えているようだ。ただしそれは決して、独立系書店の方が優れているからではない。根本的に店の在り方が異なっているから。その理由を探るためにも、まずは現状の書店という場所を俯瞰して考える必要がある。
「1ヶ月に紙の本を全く読まなくなった一方、スマートフォンに時間を費やす人が増えた」というニュースをスマホで見る。そんなシニカルな体験談からも分かるように、娯楽も知識も情報も手軽に持ち運ぶことができるスマホは現代人の必需品。電車での移動時間にも、カフェでの待ち合わせ時間にも、本はすでに必要とされていない。アプリをダウンロードすればスマホは電子書籍を読むためのデバイスにもなる。その影響か、紙よりも電子との相性が良い雑誌やコミックの販売売上は年々減少している。
「スマホが日常、読書が非日常」の世の中であっても、読書を日常とし、手触りのある紙の本を好む人たちもまだまだ健在だ。しかし、そういう本好きが書店に足しげく通っているかと言えば、そうでもなさそうだ。世代間で差はあると思うが、彼らにとって一番身近なのはゼロ距離の総合書店、Amazon。古書や洋書も合わせれば大型書店を凌駕する圧倒的な品揃え。検索ワードさえ分かれば目的の本に瞬時に辿り着き、数日以内に手元に届く。書店に行くことではなく、読みたい本を手に入れることが目的であるなら、Amazonほど便利な書店はないだろう。つまり、読書を日常とする人にとって「Amazonが日常、リアル書店が非日常」となっている。通勤通学の途中や生活圏内に書店がない場合、Amazonはさらに日常に溶け込んでいく。

Amazonにできない非日常体験を提供すること。リアル書店はここに力を注いでいかなくてはならない。1つ目は「手にとって読める」という体験。普段リアル書店で本を買う人にとっては当たり前のことだけど「実物を手に取る」ということが非日常になっていく。これはどんなリアル書店にも備わっているシンプルな強みで、Amazonにはないニッチな品揃えはより効果を発揮する。2つ目は「思わぬ本と偶然出会う」という体験。出版社名や著者名ごとに区分けするのではなく、ジャンルもMIXさせたクロスオーバーな本の並び、いわゆる文脈棚には、閲覧履歴から導き出すリコメンド機能にはできない、未知との出会いを提供することができる。3つ目は「人と出会う」という体験。著者のトークイベントやサイン会、読書会やビブリオバトルなど、本を介した人との出会いはリアルな場所にしかできない最大の強みだ。そこにはつながりが生まれ、継続していくことでコミュニティも広がっていく。
独立系書店はチェーン書店に比べて、上記の非日常体験を積極的に提供しているが、さらに存続していく理由として、決定的な違いがある。それは、独立系書店は経済的合理性だけで動いていないということだ。チェーン書店は企業である以上、前年よりも業績をあげなくてはならない。元々利益の低い本が売れない時代、社員の代わりにアルバイトを増やして人件費を削減したり、本よりも利益率の高い雑貨コーナーを増やしたり、店内にテナントを誘致して安定した賃料を確保したり、様々な施策を駆使して書店を経営している。一方で、独立系書店を始める人は純粋に利益だけを追求していないし、そういう人はそもそも本屋を始めない。こうやって書くと聞こえは良いが、「本が好きだ」「本屋をやりたい」「地元で面白いことをしたい」など、要するに感情を最優先していて、その次にどうやって店を継続させていくかを考える。本のセレクトはもちろん、内装の雰囲気やレジでのやりとりなど、良くも悪くも店主という「人」の存在が、結果としてAmazonにはできない「非日常」にも繋がっていく。
ここで言う「人」の魅力は、本来チェーン書店にも備わっていたはずなのに、皮肉にも人件費削減という企業の合理的判断が、結果として書店員の負担を増やし、その魅力を押し殺してしまっている。選書と接客という、本のプロとして、本来の能力が十分発揮できないような現場では、若手を育成する余裕もないだろう。代わりに取次会社がデータを元に配本する「売れそうな本」が店作りの根幹を担っているが、Amazonにできない「思わぬ本と偶然出会う」という体験を、どこまで提供できているだろうか。
チェーン書店が「本屋」として生き残る道があるとすれば、それはもう一度、プロフェッショナルな書店員にフォーカスすることだ。例えば、現場で働く書店員は社員ではなく、独立したプロとして契約するという仕組みを作るというのはどうだろうか。これはテナント契約している店主がオーナーとなり、本を売りたい希望者に棚を有料で貸し出して運営する下北沢のBOOK SHOP TRAVELLERや、吉祥寺のブックマンションという個人経営の本屋と同じアイデアで、プロ書店員は書店から棚を借り、書店と取引のある取次会社へ自由に発注して選書したり、個人で仕入れた本を販売することができる。その棚の販売分の利益を月々受け取る代わりに、書店には棚の使用料を支払う。魅力的な棚作りで大切なのは、現場に出向いて棚を手入れし続けることであり、定期的に通える距離で複数の書店とプロ契約できれば、書店員本来の仕事として成り立つのではないか。大雑把で勝手な妄想に聞こえるかもしれないが、チェーン書店が「本屋」として商売を続けるためには、それぐらいの思い切りが必要だと思う。
「書店がなくなることは、街にとって損失だ」と憤りの声が聞こえるうちはまだ良いのかもしれない。近い将来、街からチェーン書店がなくなったとしても、誰も困らない世の中がやってくる。そうなる前に、もう一度「本屋」であり続ける道を模索して欲しいと願うのは、自分も憤るうちの一人だからだ。

参考図書:永江朗『私は本屋が好きでした』(太郎次郎社エディタス)
ヘイト本が書店に出回る実態を取材した一冊ですが、書店業界の抱える問題についても分かりやすく詳細に説明されています。