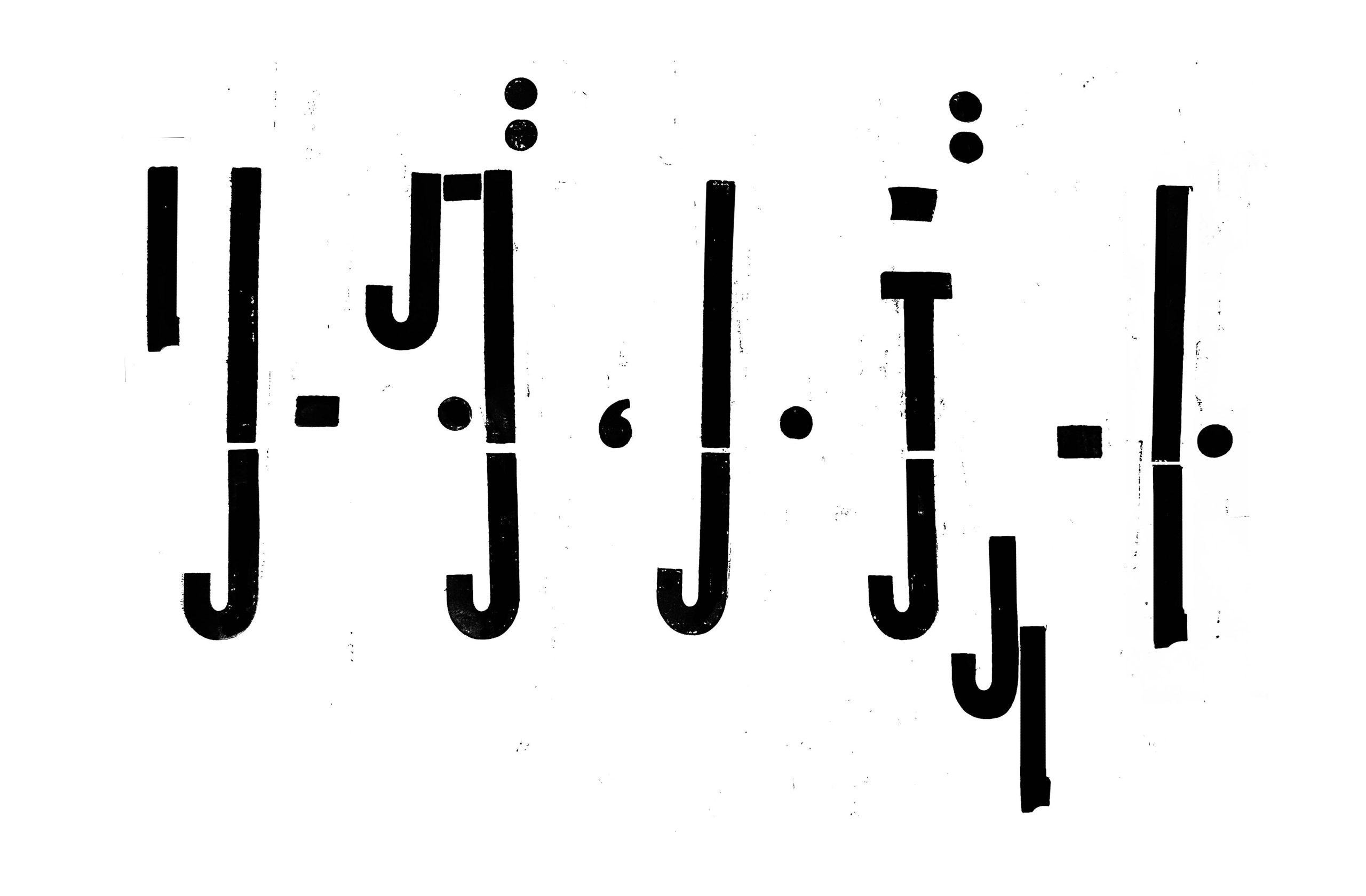Author Archive
【7/7 金】大竹昭子トークイベント「カタリココ文庫の これまでとこれから」

大竹さんがホストになり、様々なジャンルのゲストを招いたトークと朗読のイベント<カタリココ>から生まれた書籍レーベル、「カタリココ文庫」。トークを再構成した「対談シリーズ」、大竹さんによる小説、エッセイ、批評などを収めた「散文シリーズ」があります。第1期10号に続いて、第2期がスタート。その第1号として、画家・大竹伸朗さんについての書き下ろし『姓がおなじ人 極私的大竹伸朗論』が先日刊行されました。
「私はカタリココ文庫をはじめてようやく、自分のやりたいことにたどり着けたような気がしています」と語る大竹さん。今回のトークイベントでは、大竹さんにとって重要な「横断的思考」を実践できる場であるカタリココ文庫について、これまでと、そしてこれからについてお話をお聞きします。
大竹昭子(おおたけ・あきこ)
1980年代初頭にニューヨークに滞在、文章を書きはじめる。小説、エッセイ、批評など、ジャンルを横断して執筆。小説作品は、人間の内面や自我は固定されたものではなく、外部世界との関係によってさまざまに変化しうることを乾いた筆致で描き出し、幅広いファンを生んでいる。昨年7月に『図鑑少年』『随時見学可』『間取りと妄想』につづく4冊目として最新刊『いつもだれかが見ている』(亜紀書房)を上梓。 写真関係の著書も多く、『この写真がすごい』『彼らが写真を手にした切実さを』『ニューヨーク1980』などがある。写真も撮る。無類の散歩好き。
リトルプレス「カタリココ文庫」スタートを年3冊のペースで刊行するなど、個人としての活動も多い。

トークイベントの会場は、広島市中区本川町の建築事務所、Small House Design Lab.のギャラリースペース「A not B」。当店から徒歩5分のギャラリーです。
日時:7/7(金) 19:30 ~ 21:00 (受付19:00〜)
料金:1,500円
定員:30名
会場: A not B(〒730-0802 広島市中区本川町2丁目1-31岡部ビル1F Small House Design Lab.内)
【お申込み方法】
以下のコンタクトフォームに題名を「大竹昭子トークイベント」として、メッセージ本文に
1. お名前 2. 参加人数 3. 電話番号 をご記入の上お申し込みください。
また、お電話(082-961-4545)でも受付けております。
コンタクトフォームから送信できない場合、上記と同じ項目を以下のメールアドレスにお送りください。
info☆readan-deat.com ☆は@に置き換えてください。
及川静香のひとり陶器市

及川静香さんの器は、 和洋中問わず日々の家庭料理が映える普段着の器。ざざっと簡単な炒め物もぐんと美味しそうに引き立つので、日々の食卓でレギュラー選手として活躍してくれます。
及川さんは実直な人柄で黙々と仕事に取り組まれていますが、器を並べるとパッとにぎやか。素朴な粉引から色釉など様々な器を手がけています。
及川さんが作陶する益子町は陶芸の町と知られ、毎年春と秋に、大規模な陶器市が開催されています。最後の画像はこの春の陶器市での及川さんのテント風景。今回の展示も、作るよろこび、選ぶたのしみを分かち合えるような、さながらひとり陶器市の雰囲気でお伝えできればと思います。
及川静香
1982年 岩手県生まれ
2001年 益子陶芸倶楽部に勤務
2006年 益子町にて独立
2008年 益子町で新たに築窯
会期:6/3(土)〜6/18(日)
※初日作家在廊

藤本徹 朗読会『青葱を切る』

青葱を買ってくる
ひとまとめに小口切りにする
涙がでてくる
ビールを開ける
ラジオをつける
おそろしいことが聞こえてくる
青葱を切る
涙がでる
今夜は湯豆腐
明日は肉豆腐
土曜日は友人の結婚式
日曜日はライブを観に行く
そうすると
月曜日はとうぜん
ひとりでふらりと立ち飲み屋
だから来週の火曜日に
また
湯豆腐を拵えるだろう
そのときまだ
葱は腐っていないだろう
十日は余裕で日持ちする
危なくなったら冷凍すればいい
けれどそんなあいだにも
おそろしいことは進行していく
抗っているひとたちがいる
声をあげているひとたちがいる
「青葱を切る」冒頭2ページより
東京在住の詩人 藤本徹さんの詩集『青葱を切る』は、2016年に自費出版され、個人書店を中心に取り扱いが広がり、一年足らずで藤本さんの手元からすべて旅立っていきました。しばらく手に入れることができない状況が続きましたが、この本に惚れ込んだ大阪の書店 blackbird booksから、新版として昨年刊行されました。今回は藤本さんをお招きし、『青葱を切る』の朗読会を開催します。
日時:6/11(日) 17:00 ~ 18:00 (受付16:30〜)
料金:1,500円
定員: 20名
会場:READAN DEAT
【お申込み方法】
以下のコンタクトフォームに題名を「藤本さん朗読会」として、メッセージ本文に
1. お名前 2. 参加人数 3. 電話番号 をご記入の上お申し込みください。
また、お電話(082-961-4545)でも受付けております。
コンタクトフォームから送信できない場合、上記と同じ項目を以下のメールアドレスにお送りください。
info☆readan-deat.com ☆は@に置き換えてください。
万力整体室「体の声を聞くワークショップ」

万力春乃(まんりきはるの)さんがが主宰する万力整体室は、無理やり体を動かすのではなく、呼吸とイメージをつかって体の変化をうながす、施術・セッション・トークを含めた思考と実験と観察の活動。
今回のワークショップでは、座った状態でできるセルフケアと、気づいてるようで気づいていない自分の体について、万力さんの手ほどきを受けながら、言葉を通して向き合うグループセッションを行います。

万力春乃(まんりきはるの)
広島を拠点に活動する出張整体師。私たちはいつだってよりベターな状態になろうとしている、と信じている。そこに気持ちよく向かっていけるように手伝う意識で、基本の姿勢は手をそえるだけ。趣味は実験と観察とひらめくこと。整体施術以外にも疲れにくい体の使い方とセルフ整体のワークショップ、カードを使った占いや散歩をしながらのカウンセリングをおこなっている。
日時:5/30(火) 昼の部:13:00 ~ 14:30、夜の部:19:30 ~ 21:00 ※昼の部は定員となりました
料金:1,500円
定員:各10名
会場:READAN DEAT
※定員となりましたので受付終了とさせていただきます。
和井内洋介 作品展「BALE HOUSE AUTO CENTER」




なんとなく立ち寄ったスバルのディーラーで僕は圧倒されてしまった。 道路側の壁は全てガラス張りでフロアは真っ白なタイル、コインなしでコーヒーが出てくる自動販売機、ふかふかのソファ、背の高い観葉植物、そして清潔なシャツを着て忙しなく動き続けるスタッフ。
そうか、こんな世界があったのか、と、急いで車の契約書にサインし、部屋に戻り、Macintoshを開き、Google Mapsの検索窓に「Auto Center」と打ち込み、最初に目についたピンをクリックして、ストリートビューを起動させた。
僕がずっと見過ごしてきた「それ」は、つまりアメリカの本体だった。
カラリと乾いたアメリカの郊外を、よなよなGoogleストリートビューで旅する京都在住の和井内洋介さんの、カーディーラーをテーマにした作品展を開催します。会期中は作品集に加え、グッズも販売いたします。


和井内洋介
1979年宮崎生まれ。郊外好きが高じて、ストリートビューでアメリカの郊外や小さな町を巡る旅を、2011年より始める。好きな写真集はビル・オーウェンズの『サバービア』。好きなCDはアーケイド・ファイアの『ザ・サバーブス』。
会期:5/3(水)〜5/ 21(木)
5/4(木)17:00〜 「行かずに撮ろう、アメリカの旅。」
和井内洋介さんをツアーコンダクターに、スクリーンに映し出したGoogleストリートビューを見ながら、アメリカ郊外を巡ります。旅を共にするのは、誠光社・堀部篤史さん、アメリカ滞在経験もある写真家・藤岡亜弥さん。みんなで楽しい旅の思い出を作りましょう。
日時:5/4(木) 17:00 ~ 18:30 (受付16:30〜)
料金:1,500円 (配信視聴:1,000円)
定員:20名
会場:READAN DEAT
【お申込み方法】
以下のコンタクトフォームに題名を「和井内さんイベント」として、メッセージ本文に
1. お名前 2. 参加人数 3. 電話番号 をご記入の上お申し込みください。
また、お電話(082-961-4545)でも受付けております。
※オンライン視聴は受付終了とさせていただきました。
コンタクトフォームから送信できない場合、上記と同じ項目を以下のメールアドレスにお送りください。
info☆readan-deat.com ☆は@に置き換えてください。