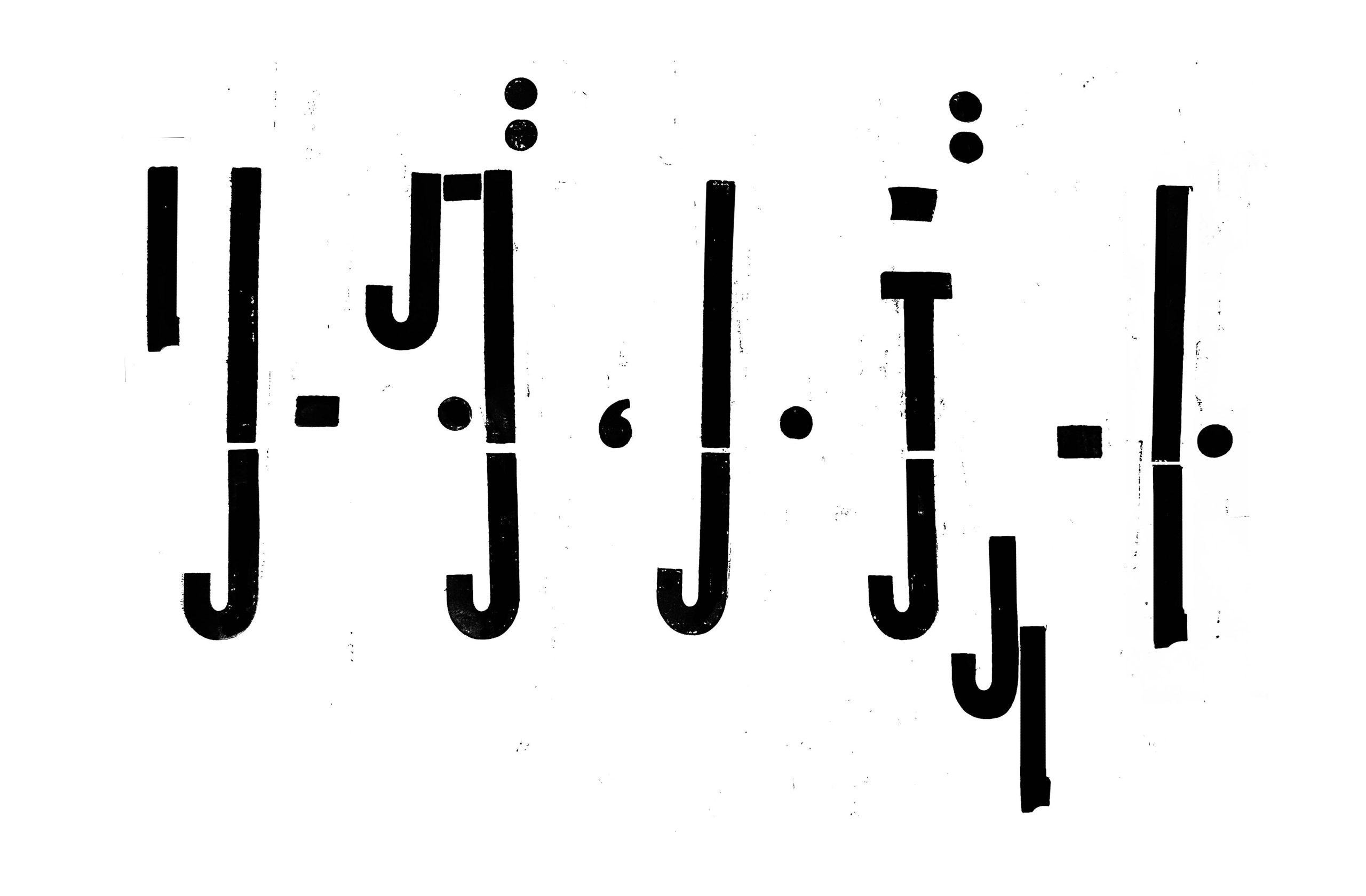Author Archive
中田雄一の白釉と色絵



白釉と色絵を基軸とした作品制作を行う、金沢在住の作家・中田雄一さんの器の取り扱いが始まりました。中田さんは焼き物の産地ではない北海道出身ということもあり、土地の固有性に左右されない、デルフト陶器を作品のエッセンスとして取り入れています。磁器のように硬く焼き締まり、つややかな光沢をたたえながら、とろりと掛けられた白釉に温かみを感じます。古典的のようでいて独創的な絵付は、洒脱な遊び心も散りばめられています。
オランダで16世紀後半から17世紀にかけて生産されたデルフト陶器は、当時の西洋で憧れの的だった中国の磁器を再現したいという思いから生まれました。材料、技術ともに磁器の生産に辿り着けなかった当時の陶工たちは、試行錯誤を重ね、中国磁器の影響も受けながら独自の表現を生み出していきます。白く焼きあがる錫釉を掛け、藍や黄色などで風車やチューリップ、人物などを描いたデルフト陶器は、磁器とはまた異なった愛らしい魅力があります。それらのいくつかは江戸時代初期の日本にも持ち込まれ、茶人たちの見立てによって珍重されました。





土そのものが好きだという中田さんは、使用する土のことを熟知した上で、当時のデルフト陶器に残された情報を読み解きながら、作品にアプローチしています。色絵の器の制作過程は、一度焼成した器に彩色を施したのちに800℃の低火度で焼き付ける、上絵付の技法が主流ですが、中田さんの色絵は、釉薬を掛けた器の上に沈みこませるように絵付を施し、一度の高火度で仕上げられています。
制作工程の定説を鵜呑みにするのではなく、当時の器を参考に仮説を立て、可能性をすくい上げていく。それは時間と労力を要する地道な作業でもありますが、焼き物だけでなく、自分の興味関心の延長線上で幅広い分野を探求する、学者肌の一面を持つ中田さんの真骨頂のようにも思えます。



新たに制作した作品も、自己表現の範疇に留めるのではなく、物として手離れすることを目指しているため、まずは一年ぐらい手元に置いて使用し、物として無理がないかを見極めるそうです。また、日常の器でありながら懐石の場でも遜色のない、ハレとケを行き来できるような器を目指す作家の姿勢に、自身の作品に対しての中立的な態度と、使い手の眼に委ねる自由さを楽しんでいるように感じます。
過去のデルフト陶器から多くのギフトを受け取っているように、「自身の作品がこの先の未来でどのように読み解かれるのか楽しみ」と語る中田さん。同時代を生きる中田さんのみずみずしい感性と、タイムレスな存在感の両方を併せ持つ器は、目にする喜び、使う愉しみも備わっています。
藤岡亜弥 写真展「Home Alone」

広島出身の写真家・藤岡亜弥さんの写真展を開催します。
いたずら好きの犬が引きおこすシリーズ「Home Alone」(1994)。会期中は「Home Alone」ポストカードセットも販売します。初日18日は西区のコーヒー豆焙煎店・MOUNT COFFEEの出張コーヒースタンド、夕方からは藤岡さんを囲んでお話を聞く茶話会も開催します。
「Home Alone」(1994年)
物語は突然始まる。
ソファの上には傷だらけの人形。
どこから見ても無惨な光景。
まるで殺人事件の暗示のよう。
ひどい! 誰がこんなことを。
恋に破れた? ギャンブルに負けた?
謎めいた世界へと引きずり込まれる。
ところが、事件は名探偵によって一気に解決される。
藤岡亜弥は物語を紡ぐ名手だ。
写真集、展覧会、写真教室でも姿勢は一貫している。
大切な1枚の写真から、大きな宇宙をつくりだす。
自らの作品について多くを語らないのは、
想像をめぐらす観客の楽しみを奪いたくないのだろう。
奈良市写真美術館で開催中の個展「New Stories」は、
十代からの作品を洗い直し、再編集した展覧会となる。
東京、台湾、欧州、米ニューヨーク、広島…。
旅する写真家が歩んできた半生が垣間見える。
「Home Alone」は、この個展で初めて発表された。
台湾渡航前、呉の実家で愛犬と過ごした思い出の断片という。
美術館からリーダンディートへ。
1994年から2022年へ。
写真は提示される場所や時代によって、
新たな呼吸を始める生き物であることを教えてもらった。
中国新聞文化担当 渡辺敬子
藤岡亜弥(フジオカアヤ)
1972年、広島県生まれ。94年日本大学芸術学部写真学科卒業。2007年文化庁新進芸術家海外派遣制度奨学生としてニューヨークに滞在。終戦後70年が経過した広島のいまをとらえた『川はゆく』で2017年第41回伊奈信男賞受賞、2018年林忠彦賞、木村伊兵衛写真賞受賞。現在広島在住。
会期:12/18(日)〜12/30(金)初日藤岡さん在廊
12/18(日)藤岡亜弥さん茶話会
藤岡亜弥さんを囲んで、作品制作のことや藤岡さんの写真集を見ながらお話をお聞きする茶話会を企画しました。MOUNT COFEEのコーヒーと、本川町のパン屋・ミサキベーカリーのシュトーレンもご用意します。アットホームな雰囲気で写真についてお話しましょう。
日時:12/18(日) 17:00 ~ 18:00
料金:1,500円(コーヒー、お菓子付き)
定員:10名
会場:READAN DEAT
【お申込み方法】
以下のコンタクトフォームに題名を「藤岡亜弥さん茶話会」として、メッセージ本文に
1. お名前 2. 参加人数 3. 電話番号 をご記入の上お申し込みください。
また、お電話(082-961-4545)でも受付けております。
コンタクトフォームから送信できない場合、上記と同じ項目を以下のメールアドレスにお送りください。
info☆readan-deat.com ☆は@に置き換えてください。
【12/19 月】石川直樹トークイベント「2022ヒマラヤ遠征報告会」

写真家・石川直樹さんが、4月から10月にかけて行った本年度のヒマラヤ遠征についてのトークイベントを開催します。
4月のダウラギリに始まり、5月にカンチェンジュンガ、7月にK2、ブロードピーク、9月にマナスルと、驚異的なペースで8,000m峰の登頂に成功しました。これまでにない今回の連続遠征は、石川さんにとってどのような経験であったのか。スライドを交えながらお話をお聞きします。
トーク終了後は、12月刊行予定の最新写真集2冊のサイン会を予定しています。
石川直樹 Naoki Ishikawa
1977年東京生まれ。写真家。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。人類学、民俗学などの領域に関心を持ち、辺境から都市まであらゆる場所を旅しながら、作品を発表し続けている。2008年『NEW DIMENSION』(赤々舎)、『POLAR』(リトルモア)により日本写真協会賞新人賞、講談社出版文化賞。2011年『CORONA』(青土社)により土門拳賞を受賞。2020年『EVEREST』(CCCメディアハウス)、『まれびと』(小学館)により日本写真協会賞作家賞を受賞した。著書に、開高健ノンフィクション賞を受賞した『最後の冒険家』(集英社)ほか多数。2016年に水戸芸術館ではじまった大規模な個展『この星の光の地図を写す』が、新潟市美術館、市原湖畔美術館、高知県立美術館、北九州市立美術館、東京オペラシティ アートギャラリーに巡回。同名の写真集も刊行された。2020年には『たくさんのふしぎ/アラスカで一番高い山』(福音館書店)、『増補版 富士山にのぼる』(アリス館)を出版し、写真絵本の制作にも力を入れている。近刊に、コロナ禍の東京・渋谷を撮影した『STREETS ARE MINE』(大和書房)など。

トークイベントの会場は、広島市中区本川町の建築事務所、Small House Design Lab.のギャラリースペース「A not B」。当店から徒歩5分のギャラリーです。
日時:12/19(月) 19:30 ~ 21:00 (受付19:00〜)
料金:1,500円
定員:30名
会場: A not B(〒730-0802 広島市中区本川町2丁目1-31岡部ビル1F Small House Design Lab.内)
【お申込み方法】
以下のコンタクトフォームに題名を「石川直樹トークイベント」として、メッセージ本文に
1. お名前 2. 参加人数 3. 電話番号 をご記入の上お申し込みください。
また、お電話(082-961-4545)でも受付けております。
コンタクトフォームから送信できない場合、上記と同じ項目を以下のメールアドレスにお送りください。
info☆readan-deat.com ☆は@に置き換えてください。
ノッティングの椅子敷展


倉敷で民藝運動を牽引した染織家・外村吉之介が考案したノッティングの椅子敷。座り心地はやわらかく、あたたか。丈夫なので永年愛用していただけるウールの織物です。
倉敷本染手織研究所を卒業し、東広島で制作を行う駒木根圭子さんの椅子敷は、民藝の精神に敬意を払いながらも、現代的なエッセンスを取り入れた図案で、暮らしに彩りを与えてくれます。手触りを楽しみながら、お気に入りをお選びください。
ノッティングの椅子敷展
12/3(土)〜11(日)※会期中無休
河合浩×宮入圭太 型染布「dessin est sain」


画家 河合浩さんの図案をもとに、染色家 宮入圭太さんが制作した型染めの布作品「dessin est sain “絵ハ健康的”」。この作品を制作するきっかけとなったのは、ちょうど2年前の2020年秋、河合さんと出会った際にいただいたオリジナルの手ぬぐいを見たときでした。「型染めで河合さんの絵を見てみたい」。そこから、型染めを引き受けてくれる作家の方を探し始めました。
宮入圭太さんは、元フィギュア原型師という異色の経歴をもつ染色家。著名なグラフィティアーティスト バリー・マッギー氏の個展で、お友達コーナーに作品が飾られていたり、一方で民藝関係のお仕事も手がけられていたり、決められた枠に収まらないスタイルをSNSで知り、「この人だ!」と鼻息荒く連絡しました。折しもコロナ禍で、打ち合わせはzoomが中心でしたが、宮入さんから型染めについて教えてもらい、河合さん本人が気に入った図案を元に、宮入さんによる制作が行われました。
河合さんと宮入さんには共通点があります。二人とも、絵や染色について専門教育を受けたり、特定の師匠のもとで修行したという経験はありません。独学を追求し、自身の表現とストレートに向き合っているからこそ、作品から独創性が溢れ出しています。そんなお二人だからこそ、この型染には二人の存在感が凝縮されています。
河合 浩 / KAWAI Yutaka
画家。東京都出身。栃木県益子在住。2010年代より本格的に絵画制作に取り組み、現在は、CDジャケット、アパレル、雑誌へのアートワーク等を手掛けるほか、日々絵を描き、全国各地で展示活動中。制作と生活の場が一体となった古い一軒家で、膨大な量のドローイング、ペインティング作品を日々描き続けている。
宮入 圭太 / MIYAIRI Keita
染色家。東京都出身。10代から20代まではグラフィティアートに傾倒し、ソフトビニール製玩具原型師をへて、型染めの世界に入る。2021年に九段下のインテリアショップ「Pacifica Collectives」で初個展を開き、作品は世界最前線のアートシーンへ。
“dessin est sain (painting is healthy)” is a stencil-dyed fabric work which designed by the artist Yutaka Kawai and dyed by the dyeing artist Keita Miyairi. when I met Kawai two years ago, he gave me a tenugui (Japanese towel) dyed with his pattern. It made me want to see bigger and more colorful fabric as his work. From there, I started looking for a dyeing artist.
Keita Miyairi is a dyeing artist with a unique background as a former figure prototype maker. His work was displayed in the “friends corner” at the solo exhibition of famous graffiti artist Barry McGee, and also he works in the field of Mingei (folk art). He willingly accepted a collaboration with Kawai. Although our meetings were mainly via Zoom, Miyairi taught us about katazome (stencil dyeing). Kawai designed several pattern, and choose one of them he liked. Then, Miyairi dyed the pattern on an Indian cloth.
Kawai and Miyairi have something in common. Neither of them has received any specialized training in painting or dyeing, nor have they trained under a particular master. Their works are overflowing with originality because they are self-taught and straightforward with their own expression. It is precisely because they are two such people that their presence is concentrated in this katazome.
KAWAI Yutaka
Painting artist. Born in Tokyo and currently resides in Mashiko, Tochigi Prefecture. He has been seriously involved in painting since the 2010s, and is currently involved in CD jackets, apparel, and magazine artwork, as well as daily drawing and exhibiting throughout Japan. In an old house where he combines production and living space, he continues to create a vast amount of drawings and paintings on a daily basis.
MIYAIRI Keita
Dyeing artist. Born in Tokyo. He was a graffiti artist from his teens to his 20s, and after working as a soft vinyl toy prototype maker, he entered the world of stencil dyeing. 2021 saw his first solo exhibition at Pacifica Collectives, an interior design store in Kudanshita, bringing his work to the forefront of the international art scene.

サイズ:約W580 x H1030 mm
素材:インド綿
図案:河合浩
型染:宮入圭太
上下木製軸棒 付属
エディション:4
size:aprx.W580 x H1030 mm
fabric:Indian cotton
designed by Yutaka Kawai
stencil dyeing by Keita Miyairi
upper & lower wooden shaft rod included
edition:4
遠方のお客様にもお買い求めいただけます。詳しくはメールにてお問い合わせください。
International shipping is available. Please contact us.