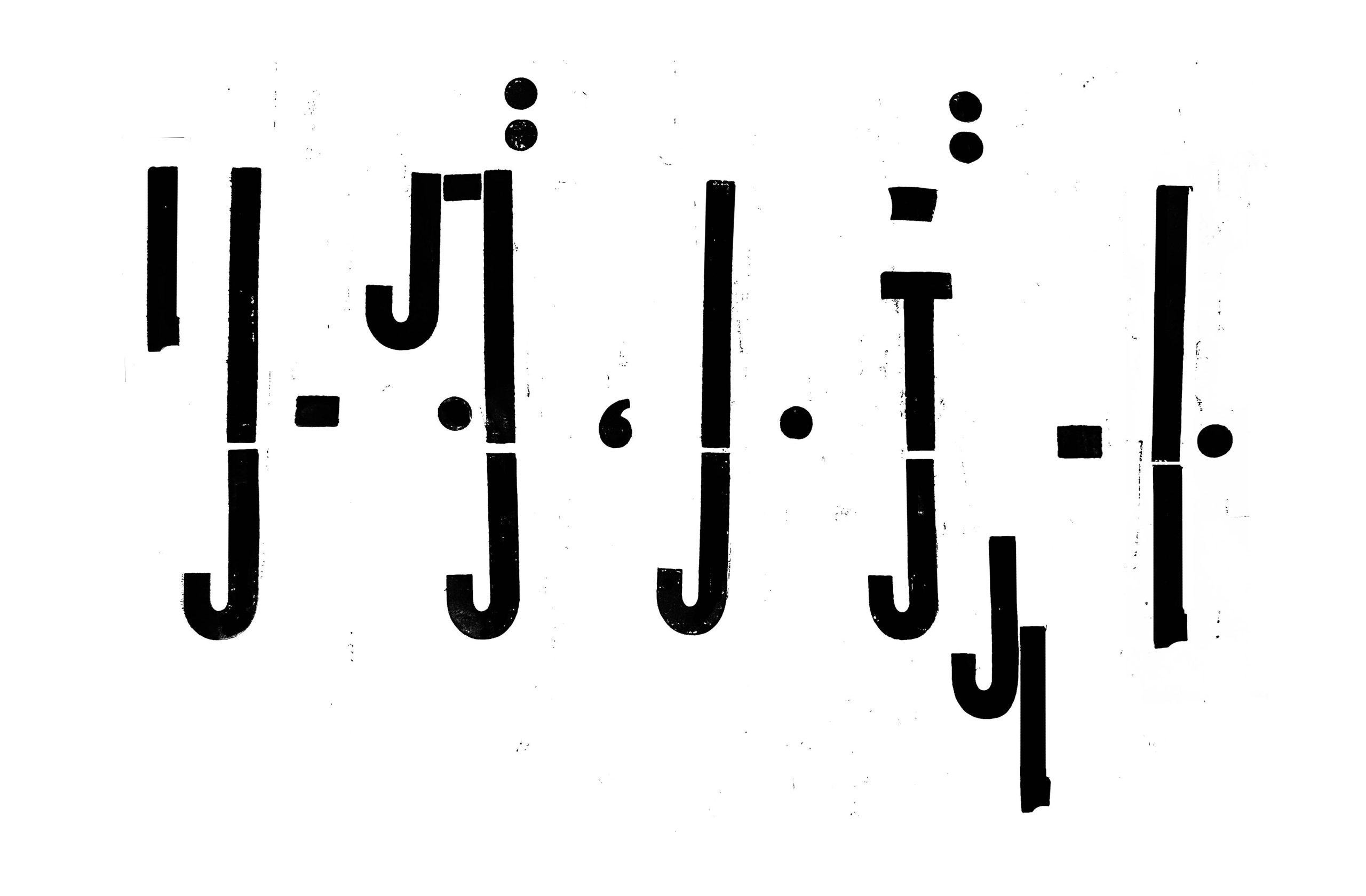Author Archive
いのちの花、希望のうた




 画家と詩人の兄弟ふたりによる画詩集『いのちの花、希望のうた』。
画家と詩人の兄弟ふたりによる画詩集『いのちの花、希望のうた』。
兄の岩崎健一が描く花は、花弁の一枚、葉脈の一筋までを丹念に緻密に捉えていて、慎ましくも力強く輝いています。鮮やかな色彩はいのちを咲かせる喜びの色。画家の花への敬愛が伝わってきます。
弟の岩崎航の五行詩は、勇気と希望と慈しみのうた。病と向き合い、日々の営みのなかで生まれた、五行の短い言葉の連なりは、目で耳で再生されるたび心の奥で響きます。

筋ジストロフィーという、身体の筋肉が壊れやすく再生されにくい難病を抱えながら暮らす二人の絵と詩は、生きた証として、また生きる中で見出した光として創作されたもの。自分自身と向き合うための純粋な創作活動はストレートに胸を打ちます。
あなたへの、そして大切に思う誰かへの花束として。
1,700+税 (WEB SHOP)
みんぱくの図録

文化人類学・民族学の研究所であり、世界最大級の博物館機能を備えた国立民族学博物館、通称みんぱくの展覧会図録がいくつか入荷しました。



 『太陽の塔からみんぱくへ – 70年万博収集資料』 ¥1,600+税
『太陽の塔からみんぱくへ – 70年万博収集資料』 ¥1,600+税
大阪万博を2年後に控えた1968年、世界の諸民族の資料を収集するというミッションに限られた予算と時間のなかで取り組んだ「万博資料収集団」。彼らが1968年から1969年にかけて収集した世界各地の標本資料や活動の様子を紹介した一冊。60年代後半から70年代にかけて世界が大きく動いていく状況のなかでの民族文化や地域社会の様相を描き出す。



 『イメージの力』 ¥1,600+税
『イメージの力』 ¥1,600+税
歴史を通じて人間が生み出してきた様々なイメージ。そのつくり方や受けとめ方に、人類共通の普遍性はあるのか。 みんぱくが所蔵するコレクションのなかから約600点の造形を精選。



 『ビーズ』 ¥1,100+税
『ビーズ』 ¥1,100+税
飾り玉、数珠玉、トンボ玉などを総称するビーズ。人類がつくりだした最高の傑作品のひとつであるビーズについて、つくる楽しみ、飾る楽しみをとおして世界の人びとにとってのビーズの魅力を紹介。



 『現れよ。森羅の生命 – 木彫家 藤戸竹喜の世界』 ¥1,800+税
『現れよ。森羅の生命 – 木彫家 藤戸竹喜の世界』 ¥1,800+税
旭川を拠点に「熊彫り」を生業としていた父のもとで、12歳から木彫を始めた藤戸竹喜(ふじと たけき)は、父祖の彫りの技を受け継ぎながら、熊をはじめ狼やラッコといった北の動物たちと、アイヌ文化を伝承してきた先人たちの姿を木に刻み、繊細さと大胆さが交差する独自の世界を構築。卓抜なイメージ力・構想力とともに、生命あるものへの深い愛情に根ざした生気あふれる写実表現。 動物たちの俊敏な動きをとらえた初期作から、民族の歴史と威厳をモニュメンタルに伝える等身大人物像まで、70年にわたる創作活動の軌跡とその背景をたどった作品集。



 『屋根裏部屋の博物館』 ¥2,762+税
『屋根裏部屋の博物館』 ¥2,762+税
実業家・渋沢敬三が学問への憧れを捨て去れず、自邸内の物置にアチックミューゼアム(屋根裏部屋の博物館)を設け、玩具から始まり、庶民の生活資料の収集と調査を行った。このような資料を渋沢は「民具」と命名し、日本の民具研究から周辺諸民族の物質文化の比較研究へと研究領域をひろげ、独自の渋沢民俗学を形成した。アチックミューゼアムの民具と民具研究の思想がうかがえる一冊。


 『なかはどうなってるの? 民族資料をX線でみたら』 ¥667+税
『なかはどうなってるの? 民族資料をX線でみたら』 ¥667+税
人間が多様な素材からつくる道具の数々をX線写真で観察すると…。モノのもつ魅力のあらたな発見。 民族資料にX線透視調査を行い、実物とX線写真を比較しながら,モノの中に秘められた様々な側面を紹介。外見たけでは気がつかなかった発見や、これまでとは違ったモノの見方ができる一冊。
今日、世界の辺境・秘境へ手元のスマホ画面のなかでも訪れることができますが、もう一歩深く分け入りたいと思ったとき、みんぱくを訪れて文化の多様性を肌で感じてみるのもいいかもしれません。テクノロジーの進歩とともに手放してしまうには惜しい人類の英知の一端、まずは図録で探求してみてください。
川はゆく


 写真家にとって広島をテーマにすることは「ヒロシマ」を表現することと切り離せない。土門拳は『ヒロシマ』(1958)で被爆者を通してその非人道性をあぶり出し、石黒健治は『広島』(1970)で高度経済成長下で風化する記憶を淡々と描写し、76年に撮り始めた土田ヒロミのヒロシマ三部作は年月をかけた記録写真で、石内都の『ひろしま』(2008)は静かに美しく被爆遺品をとらえた亡き人のポートレート。
写真家にとって広島をテーマにすることは「ヒロシマ」を表現することと切り離せない。土門拳は『ヒロシマ』(1958)で被爆者を通してその非人道性をあぶり出し、石黒健治は『広島』(1970)で高度経済成長下で風化する記憶を淡々と描写し、76年に撮り始めた土田ヒロミのヒロシマ三部作は年月をかけた記録写真で、石内都の『ひろしま』(2008)は静かに美しく被爆遺品をとらえた亡き人のポートレート。
そして戦後70年が過ぎた現在の広島を撮り下ろした写真家・藤岡亜弥さんの『川はゆく』(2017)。マツダスタジアムを埋め尽くすカープファン、賑やかなフラワーフェステバル、路面電車、本通り商店街、基町アパート、テレビに映った大統領当選のニュース、燃えるような夕焼け。広島にいるとなかなか気づかないけれど、どの風景もヒロシマ。市内を流れる川の流れのように、この瞬間も絶えず時代とともに街も人も流れている。
広島生まれの藤岡さんが向き合い生まれたこの写真集は数年後、どのような意味を投げかけてくるのでしょうか。
『川はゆく』¥5,000+税
アオザイ通信で読む写真とベトナム




 漫画家・西島大介さんが描く『ディエンビエンフー』の舞台・ベトナムを、食・文化・歴史・戦争といったテーマで紹介する、コミックエッセイ『アオザイ通信完全版』。今回ギャラリースペースでは、生原画の展示に併せて、『アオザイ通信完全版』に写真を提供し、最新写真集『光の粒子』を刊行した写真家・かくたみほさんがとらえたベトナムの写真を展示します。
漫画家・西島大介さんが描く『ディエンビエンフー』の舞台・ベトナムを、食・文化・歴史・戦争といったテーマで紹介する、コミックエッセイ『アオザイ通信完全版』。今回ギャラリースペースでは、生原画の展示に併せて、『アオザイ通信完全版』に写真を提供し、最新写真集『光の粒子』を刊行した写真家・かくたみほさんがとらえたベトナムの写真を展示します。
西島大介 / Daisuke Nishijima
1974年東京都生まれ。広島在住。2004年描き下ろし単行本『凹村戦争』で漫画家としてデビュー。他作品に『世界の終わりの魔法使い』『Young, Alive, in Love』など。2012年の作品『すべてがちょっとずつ優しい世界』では第三回広島本大賞を受賞。ベトナム戦争を描いた長編『ディエンビエンフー』(2007〜)は12巻を刊行するも掲載誌休刊のため未完だったが、双葉社へ移籍し完結編『ディエンビエンフー TRUE END』(2017〜)として連載中。年内完結予定。
daisukenishijima.jimdo.com
かくたみほ / Miho Kakuta
1977年三重県生まれ。リンネル、OZマガジン、ダ・ヴィンチなど様々な雑誌の他にSPITZや、きのこ帝国のCDジャケット、ファッションブランドのカタログ、ほぼ日のWEBなどでも光を活かした作風で活動中。教則本著書には「写真の撮り方きほんBOOK、「ふんわりかわいい写真の撮り方ノート」などがある。ライフワークではフィルムカメラを愛用しており10年以上フィンランドに通い作品制作をした写真集に「MOIMOI そばにいる」、「光の粒子」がある。
www.mihokakuta.com
instagram:mihokakuta
会期:5/26(土)〜6/10(日)
【6/2 土】トークイベント
西島大介的写真講義 〜ブレッソン/キャパ/澤田教一/かくたみほ まで〜
ディエンビエンフーの主人公・ヒカルミナミはベトナムに配属された報道カメラマンでもあり、写真は西島さんにとって重要なテーマでもあります。多くの資料を元に培った知識と大胆な思考のもと「ズバリ写真とは何か」に迫ります。
また当日は「アオザイ通信完全版 」1、2巻を対象としたサイン会も開催します。
日時:6/2(土)18:00〜19:30(受付17:30より)
出演:西島大介(漫画家)
料金:1000円
定員:30名
場所:READAN DEAT
【お申込み方法】
以下のコンタクトフォームに題名を「西島さんトークイベント」として、メッセージ本文に
1. お名前 2. 参加人数 3. 電話番号 をご記入の上お申し込みください。また、お電話(082-961-4545)でも受付けております。
コンタクトフォームから送信できない場合、上記と同じ項目を以下のメールアドレスにお送りください。
info☆readan-deat.com ☆は@に置き換えてください。
星を継ぐものートーテムポールに宿る神話の世界

 アラスカやカナダの神話と日本をつなぐ旅について、スライドを交えたトークイベントを開催します。スピーカーは、アラスカやカナダの先住民と深い親交を持つ写真家・赤阪友昭さん。20年以上にわたる旅の中で感じてきたアラスカと日本の神話的繋がりとは?
アラスカやカナダの神話と日本をつなぐ旅について、スライドを交えたトークイベントを開催します。スピーカーは、アラスカやカナダの先住民と深い親交を持つ写真家・赤阪友昭さん。20年以上にわたる旅の中で感じてきたアラスカと日本の神話的繋がりとは?
キーワードは、トーテムポールと縄文です。2000 年、南東アラスカ先住民のクリンギットの古老とアイヌの人々の神話の交流を目的とした文化交流プロジェクト 『神話を語り継ぐ人々』を北海道、熊野、明治神宮の地で開催しました。そのときにアラスカ先住民クリンギットに伝わるおよそ一万年前の神話、そして、アイヌとアラスカをつなぐ伝承について知りました。それは驚くことに私たち日本人に残された神話にも通じている物語だったのです。
私たちの祖先たちが辿った旅の軌跡について、アラスカの神話や写真家・星野道夫とのエピソードを交えながらお話しします。日本の古層に残された縄文的世界とアラスカ先住民族のつながりを未来へむけて継ぐ-そんな時間をみなさんと分かち合いたいと思います。
また、会の最後に、赤阪が制作中の映画『銀鏡 SHIROMI』についてお話をいたします。この映画は日本の古層に秘められた星への祈りとそれを守り続けてきた神楽の里の物語です、星への祈りが、実は縄文時代から連綿と続いてきたものであり、それは私たちをつぎの時代へと導く羅針盤の北極星となるかもしれない、というお話です。アラスカ先住民の神話がそうであるように、神話は単なる作り話ではなく、本当にあった話であることを教えてくれるのです。
赤阪友昭(あかさか・ともあき)
1963年 大阪市生まれ。1995年の阪神淡路大震災を機に写真家に転身する。1996年、モンゴルの遊牧民やアラスカ先住民との暮らしから撮影をはじめ、被写体に寄り添いながら長期にわたる取材活動を実施している。雑誌「コヨーテ」等に写真と文を寄稿し、NHKの番組制作、プラネタリウムのプログラム制作や国立民族学博物館での企画写真展、アイヌとアラスカ先住民の国際交流プロジェクトのプロデュースなど活動は多岐にわたる。東北の震災後は、文化庁の支援を受けた福島県立博物館の被災地支援プロジェクト「はま・なか・あいづ文化連携プロジェクト」に参加し、変動し続ける福島の自然環境、特に立入制限区域内のランドスケープの記録撮影を続け、映像記録「水の記憶、土の記憶ー南相馬から」を南相馬市と共同制作する。また、福島の自然環境を再認識するために招聘したオランダのドキュメンタリー映画「新しい野生の地ーリワイルディング」は日本全国で劇場公開され、現在も各地で自主上映が続いている。現在は、国内外に残された原初の信仰、縄文文化や祭祀儀礼をテーマに撮影・取材。東京及び各地方においてスライドやトーク、講演活動などを定期的に開催。2009年より写真ギャラリー「photo gallery Sai」(大阪市福島区)を主宰。著作に北米海岸の先住民と向き合った10年をまとめた『TheMyth – 神話の風景から – 』(松本工房刊)がある。
www.akasakatomoaki.net
【日時】2018/5/28(月)19:30~21:00(受付19:00より)
【料金】1,500円
【定員】30名
【会場】READAN DEAT
【お申込み方法】
以下のコンタクトフォームに題名を「星を継ぐものトークイベント」として、メッセージ本文に
1. お名前 2. 参加人数 3. 電話番号 をご記入の上お申し込みください。また、お電話(082-961-4545)でも受付けております。
コンタクトフォームから送信できない場合、上記と同じ項目を以下のメールアドレスにお送りください。
info☆readan-deat.com ☆は@に置き換えてください。