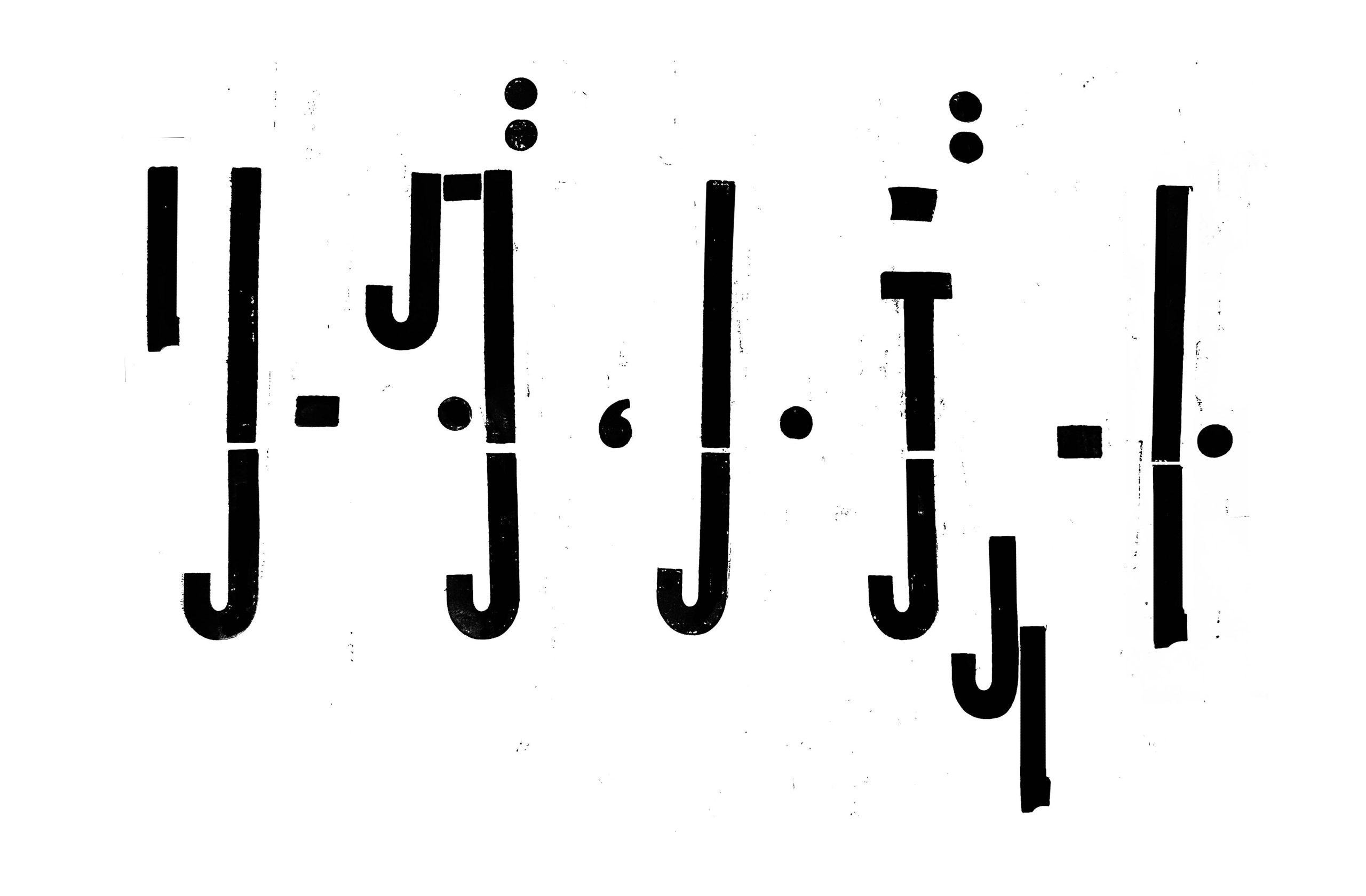THANK YOU
チェーン書店が街から消えていく

そう聞いて憤る方も多いかもしれないが、個人的にはそう考えている。その流れは人口の少ない地域から徐々に都市部へと広がっていく。地場で頑張る中規模のチェーン書店は本屋であることを諦め、全国チェーンの大型書店も採算の取れなくなった地方都市から順に撤退をはじめる。その一方でポツポツと増えていくのは「独立系書店」と呼ばれる個人経営の本屋で、全国的に見てもここ最近、実際に増えているようだ。ただしそれは決して、独立系書店の方が優れているからではない。根本的に店の在り方が異なっているから。その理由を探るためにも、まずは現状の書店という場所を俯瞰して考える必要がある。
「1ヶ月に紙の本を全く読まなくなった一方、スマートフォンに時間を費やす人が増えた」というニュースをスマホで見る。そんなシニカルな体験談からも分かるように、娯楽も知識も情報も手軽に持ち運ぶことができるスマホは現代人の必需品。電車での移動時間にも、カフェでの待ち合わせ時間にも、本はすでに必要とされていない。アプリをダウンロードすればスマホは電子書籍を読むためのデバイスにもなる。その影響か、紙よりも電子との相性が良い雑誌やコミックの販売売上は年々減少している。
「スマホが日常、読書が非日常」の世の中であっても、読書を日常とし、手触りのある紙の本を好む人たちもまだまだ健在だ。しかし、そういう本好きが書店に足しげく通っているかと言えば、そうでもなさそうだ。世代間で差はあると思うが、彼らにとって一番身近なのはゼロ距離の総合書店、Amazon。古書や洋書も合わせれば大型書店を凌駕する圧倒的な品揃え。検索ワードさえ分かれば目的の本に瞬時に辿り着き、数日以内に手元に届く。書店に行くことではなく、読みたい本を手に入れることが目的であるなら、Amazonほど便利な書店はないだろう。つまり、読書を日常とする人にとって「Amazonが日常、リアル書店が非日常」となっている。通勤通学の途中や生活圏内に書店がない場合、Amazonはさらに日常に溶け込んでいく。

Amazonにできない非日常体験を提供すること。リアル書店はここに力を注いでいかなくてはならない。1つ目は「手にとって読める」という体験。普段リアル書店で本を買う人にとっては当たり前のことだけど「実物を手に取る」ということが非日常になっていく。これはどんなリアル書店にも備わっているシンプルな強みで、Amazonにはないニッチな品揃えはより効果を発揮する。2つ目は「思わぬ本と偶然出会う」という体験。出版社名や著者名ごとに区分けするのではなく、ジャンルもMIXさせたクロスオーバーな本の並び、いわゆる文脈棚には、閲覧履歴から導き出すリコメンド機能にはできない、未知との出会いを提供することができる。3つ目は「人と出会う」という体験。著者のトークイベントやサイン会、読書会やビブリオバトルなど、本を介した人との出会いはリアルな場所にしかできない最大の強みだ。そこにはつながりが生まれ、継続していくことでコミュニティも広がっていく。
独立系書店はチェーン書店に比べて、上記の非日常体験を積極的に提供しているが、さらに存続していく理由として、決定的な違いがある。それは、独立系書店は経済的合理性だけで動いていないということだ。チェーン書店は企業である以上、前年よりも業績をあげなくてはならない。元々利益の低い本が売れない時代、社員の代わりにアルバイトを増やして人件費を削減したり、本よりも利益率の高い雑貨コーナーを増やしたり、店内にテナントを誘致して安定した賃料を確保したり、様々な施策を駆使して書店を経営している。一方で、独立系書店を始める人は純粋に利益だけを追求していないし、そういう人はそもそも本屋を始めない。こうやって書くと聞こえは良いが、「本が好きだ」「本屋をやりたい」「地元で面白いことをしたい」など、要するに感情を最優先していて、その次にどうやって店を継続させていくかを考える。本のセレクトはもちろん、内装の雰囲気やレジでのやりとりなど、良くも悪くも店主という「人」の存在が、結果としてAmazonにはできない「非日常」にも繋がっていく。
ここで言う「人」の魅力は、本来チェーン書店にも備わっていたはずなのに、皮肉にも人件費削減という企業の合理的判断が、結果として書店員の負担を増やし、その魅力を押し殺してしまっている。選書と接客という、本のプロとして、本来の能力が十分発揮できないような現場では、若手を育成する余裕もないだろう。代わりに取次会社がデータを元に配本する「売れそうな本」が店作りの根幹を担っているが、Amazonにできない「思わぬ本と偶然出会う」という体験を、どこまで提供できているだろうか。
チェーン書店が「本屋」として生き残る道があるとすれば、それはもう一度、プロフェッショナルな書店員にフォーカスすることだ。例えば、現場で働く書店員は社員ではなく、独立したプロとして契約するという仕組みを作るというのはどうだろうか。これはテナント契約している店主がオーナーとなり、本を売りたい希望者に棚を有料で貸し出して運営する下北沢のBOOK SHOP TRAVELLERや、吉祥寺のブックマンションという個人経営の本屋と同じアイデアで、プロ書店員は書店から棚を借り、書店と取引のある取次会社へ自由に発注して選書したり、個人で仕入れた本を販売することができる。その棚の販売分の利益を月々受け取る代わりに、書店には棚の使用料を支払う。魅力的な棚作りで大切なのは、現場に出向いて棚を手入れし続けることであり、定期的に通える距離で複数の書店とプロ契約できれば、書店員本来の仕事として成り立つのではないか。大雑把で勝手な妄想に聞こえるかもしれないが、チェーン書店が「本屋」として商売を続けるためには、それぐらいの思い切りが必要だと思う。
「書店がなくなることは、街にとって損失だ」と憤りの声が聞こえるうちはまだ良いのかもしれない。近い将来、街からチェーン書店がなくなったとしても、誰も困らない世の中がやってくる。そうなる前に、もう一度「本屋」であり続ける道を模索して欲しいと願うのは、自分も憤るうちの一人だからだ。

参考図書:永江朗『私は本屋が好きでした』(太郎次郎社エディタス)
ヘイト本が書店に出回る実態を取材した一冊ですが、書店業界の抱える問題についても分かりやすく詳細に説明されています。
BE HAPPY in 2019 & 2020

毎年アっという間に一年が終わりがちですが、今年は本当にアっという間、半角で表現したくなるほど例年よりも早く感じました。それもそのはずで、振り返ると展覧会やトークイベントなど合わせて計34本の企画を開催、さらに毎月(6月・12月はお休み)ゲストを招いた茶話会企画・ナイトREADAN DEATも加えると本当に毎月たくさんのイベントがありました。
6/18には5周年を迎えることができ、企画商品「HOSHIMADO」もお披露目。5年前には想像できなかった沢山の出会いに支えられています。
今年は店の外でもトークイベントに呼んでいただくことが多い一年でした。いずれも広島で本にまつわるイベントを企画する「あいだproject」さん主催のイベント。本に関わる個性派な人たちとの出会いは純粋に楽しい!
9月にオープンした三川町のホテル「KIRO」の選書もさせてもらいました。広島をベースに活動する人が多く関わっていて、こうしてメンバーとして参加できることが嬉しいです。
また、今年は当店から徒歩1分の距離にある建築事務所・SHDL内のギャラリー「A not B」で展示やトークイベントを企画させてもらえたことも非常に大きな変化で、企画できる内容の幅がグッと広がりました。2020年も色々と企画進行中です。
足早に振り返ってみましたが、2019年は新しい経験をさせてもらうことができ、次の年に繋がる土壌づくりにもなりました。
ちなみに1月のラインナップは、
トークイベント
1/19(日)坂口恭平さん
1/24(金)石川直樹さん
企画展
1/12(土)〜13(日)shink tankという輸入雑貨店のPOP-UP SHOP
1/18(土)〜26(日)ノッティングの椅子敷展
となっています。ナイトREADAN DEATも毎月ではなくなりますが、2020年も継続して開催していきます。
店を通してBe happyを共有するアーティストTHOMAS KONGのように、2020年もお客さんと一緒に自分自身も楽しみつつ精進していきたいと思います。

THOMAS KONG
https://thomaskong.biz/
ブーメランを投げてでも

ずらり並んだ器の中からどうしてそれに惹かれたのか自分自身でもよく分からない。作家の名前も分からずに初めて買った陶のフリーカップ。その理由を求めて、全国のギャラリーのWEBサイトをチェックしたり、店に足を運んだり、いわゆる作家物の器を追いかけるようになった20代後半。それらは当時まだ名付けされていなかった「生活工芸」の器だった。
生活工芸とは何か。新潮社刊行の『工芸批評』『工芸青花 7号』を参照にしながらざっくりまとめると、高額で権威的な一点物である「鑑賞工芸」に対して、リーズナブルで定番商品として買い足すことができるシンプルな作家の器を「生活工芸」と呼ぶようになった。発信力のある数名の作家が自らカテゴライズした生活工芸、そのキーワードは丁寧な暮らし。2000年代に次々と創刊された暮らし系雑誌が後押しする形で、これまで男性が主体となって論じてきた鑑賞工芸とは全く別の、保守的なイメージから解放された、ナチュラルなライフスタイルに馴染むセンスの良い工芸、それが生活工芸だ。
『工芸批評』は、その生活工芸のフィールドにあえて批評を持ち込もうという試みだ。うんちくの世界からせっかく解放された工芸にどうして批評が必要なのか。それは裾野を広げたその先で繰り広げられる出来事に、飽き飽きと、そして辟易させられている人たちが少なからずいるからではないだろうか。
「あの人が雑誌で紹介したあの作家の器が欲しい!」手仕事の希少性は購買欲を刺激する。知識よりも感性が重視され、買いやすい価格帯の生活工芸は、鑑賞工芸と比べるまでもなく商品として扱いやすい。消費者の求めに応じるように、それらを取り扱う店やギャラリーは増え、その結果、新たに作家デビューする人も増えていく。
マーケットが拡がり、選択肢が増えることは喜ばしいことだけど、なぜかもやもやと不健全な空気が漂っている。なぜなら、買い手も売り手も、自分自身の「眼」を持とうとせず、付加情報ばかりに気を配っているからだ。「消費」することが目的なので、物を見ているようで見ていない。その一方で失敗したくないという心理が働き、目利きと呼ばれる他人の眼を頼る。
SNSの登場はさらに事態を加速させる。人気作家のタグが付いた、いいね待ちの投稿が世の中に溢れ、承認欲求の道具として次々と消費されている。またSNSは作家にも影響を及ぼしかねない。流行を模倣し、あえて消費されることを目指す作り手が出てくる可能性もあるだろう。クリエイティブには必然的に孤独がつきまとう。自分と対峙したその先にようやく掴むものだと思う。
生活工芸がもたらしたのは、工芸の大衆化だ。勿論そのなかには自分の眼を持った使い手も、自分の道を歩む作家もたくさんいるが、上記の推測もあながち突飛ではないと思う。だからこそ、ちゃんと物を見ようという啓蒙活動が必要であり、求められているのだと思う。物を見るときに言葉を持つということは、眼を持つことにも繋がっていく。
「ちゃんと物を見よう。」と投げかけたこの言葉は、冒頭に登場する自分自身に対してブーメランのように鋭く返ってくる。なぜそれが良いのか。どうして店で扱うのか。言語化するということは、頭の中のぼんやりとした思考を定義化し、アウトプットすることだ。感覚的に惹かれた世界を思考し、言葉で読み解いたその先に、自分の眼に辿り着く。それは「消費」以上に刺激的だ。
セレクトってなんだろう

日々トークイベントや展示会など何かしら企画しているが、本屋の本来の仕事は、本を仕入れて売ることだ。
八百屋は野菜を仕入れて売り、酒屋は酒を仕入れて売る。花屋、魚屋、眼鏡屋、レコード屋etc。小売業の役割は、市場や卸先から仕入れた商品を消費者に届けること。独自の仕入れルートや時流を読む力、そのジャンルに精通した審美眼を磨き、ライバルが真似できないような商品を取り揃える。ジャンルは違えど、小売専門店にとって品揃えこそが腕の見せどころで、そこにサービスや接客を組み合わせて集客につなげる。つまり、店の個性が反映された商品セレクトが、小売業の基本で要だ。
新刊書店で「セレクト」について考えると、店舗のスタイルによってその意味は変わってくる。まず大型書店の場合、不特定多数の来店者に向けた数百万冊の在庫数自体がセレクトであり、アート系や学術系専門書店の場合、玄人が唸るような一冊を揃えることがセレクトである。町のインディペンデント書店の場合、店主の好みや店の方向性をベースに、リトルプレスやzineに加え、取扱い可能な一般流通の書籍を組み合わせてセレクトする。売上だけのインスタントな本よりも、熱意のこもった本を選びたいと思うのは皆同じで、そういう本はSNSで入荷日にこぞって紹介されることが多々ある。それは「店の個性が反映された商品セレクト」なのだろうか、と正直思うこともある。だけど、他の店と被っていても、自信を持って選んだその一冊を誰かに届けたいという意志そのものが重要なんだと思う。

いわゆる作家もののうつわの場合、本と比べて需要と供給のバランスが異なる。一度の生産数や流通量に限りがあり、そのなかで店主の嗜好や店の志向をベースにセレクトを行う。個展を開催する店や専門のギャラリーも多い。その仕入先は作家本人であり、関係性を築く上でも店のセレクトが重視される。それを踏まえた上で、SNSのいいねの数が店の「セレクト」に影響を及ぼしていないだろうか。個人が情報発信を行い、店も作家も可視化されたニーズを手軽に読み取れる時代だからこそ、自分自身の基準がブレないよう意識する必要がある。モニターのなかの二次情報を追いかけるのではなく、自分の内から湧き上がるものに目を向けなくてはならない。
オンラインで何でも揃う成熟した消費社会において、品揃えの独自性を突き詰めると、オリジナル商品や一点物に行き着く。しかし、純粋に「セレクト」を通して、驚きや喜びを与えてくれる店もある。それは見たことのない珍しい物を選んでいるということではなく、集められた一つ一つの物から醸し出される、言わば店の文化そのものに心が動かされる。それは店主の努力とセンス、経験や勘からもたらされるもので、その本質は簡単にマネできない。本屋でもうつわ屋でもそういう店に憧れるし、二足のわらじだけど、そうなりたい。道のりは長いけれど本気でそう思っている。
六年目・六月の本屋考



6月は本屋を営む方々とトークイベントに出演する機会が重なりました。『ことばが生まれる景色』原画展のトークイベントではTitleの辻山良雄さん。5周年企画でお招きした古巣B&Bのオーナー内沼晋太郎さん。「プチ中四国本屋会議」では、高松の完全予約制の古本屋・なタ書の藤井佳之さんと、トーク会場にもなった横川の呑める古本屋・本と自由の青山修三さん。
辻山さんは自分が本屋を始めるきっかけとなった、リブロ広島店を形作った人。そのことを知ったのは、Titleオープンの少し前でした。幻冬舎ウェブマガジンの連載でも触れられていますが、時間と場所を超えて繋がっていくことが嬉しいです。連載に出てくる男性はうちにもよく来てくれるお客様で、トークイベントには奥様と一緒に参加されていて、感慨もひとしおでした。
5年前のオープン直後にもトークゲストとして来てくれた内沼さん。何かと暗い書店業界に軽やかなアイデアを提示し続けるお話はより深化していました。雑誌『ユリイカ』での論考(内沼さんのnoteに全文掲載される予定)には勇気をもらい、下北沢のまちづくりの話や精力的に取り組む出版事業の話に刺激をもらいました。
個性的な古書店を営む二人を交えた鼎談では、仕入れや売上など普段は聞けない突っ込んだ内容で盛り上がりました。古書と新刊という違いはあれど、予約制だからできる藤井さんの働き方には目から鱗で、新刊書店勤務を経て語られる青山さんの生き方に共感。二人の味わいに魅了される一夜、主催のあいだprojectさんにも感謝です。
それらのイベントを受けて最近考えた本屋考、まとめきれていないのですが、思うままに書き記してみました。
読書という行為は「視覚」、目という感覚器官を使うことであり、PCモニターやスマホと相性が良い。「視覚」を用いて知識や情報を提供する本は、紙に印刷されなくてもオンラインで何処へでも届けることができる。音楽を楽しむための「聴覚」も電子機器との相性は抜群。そもそもデジタルデータのCDが、音楽配信サービスの普及に圧されるのは道理とも言えてしまう。
しかし、0と1の二進法で構築されるコンピューターの世界。どんなに素晴らしい絵や音楽も、モニター画面上で見たもの、PCのスピーカーで聴いたものは、結局は0と1という記号の集合体であり、それを脳がそのように変換しているのではないか?そのような変換行為には無意識のうちに微細なストレスが生じているのではないか?というのは、先日のトークイベントでnakabanさんから聞いた仮説。非常に説得力のある話だと思う。原画を観る。ライブで演奏を聴く。「本物」に触れたときに感動は押し寄せる。
さらに話を進めると、PCやスマホがアクセスできない「味覚」「嗅覚」「触覚」を体感できるのは、リアルの強みだ。料理教室や読書会など「イベント」と言ってしまうと月並みだけど、本屋も五感にアクセスできる可能性を秘めている。
人との出会いもその一瞬一瞬、感覚をフル活用している。店そのものが「人」である個人店はチェーン店に比べて、店主とお客さん、お客さん同士といった関係性が生まれやすいところが魅力だと思う。もちろん「人」だからこそ相性の良し悪しはあって、苦手な店もあるけれど、そういうところも含めて面白い。お気に入りの喫茶店、仕事帰りに立ち寄るBAR、馴染みのレコード店、月に一度の床屋。そんな行きつけの場所の一つに本屋が含まれていると嬉しいし、それはとても豊かだ。
と、ここまで書いてみて、愛すべきキャラクターの店主がいつも店にいることこそ、実は一番の魅力だったりするのではと気がつきました。ゆるくてちょっとダメ(褒め言葉)でそこが格好良かったりする、二人の古書店の店主のことを思い浮かべると、どんなに本屋論を語っても結局かなわない気がします。ちょっとズルイなあ。