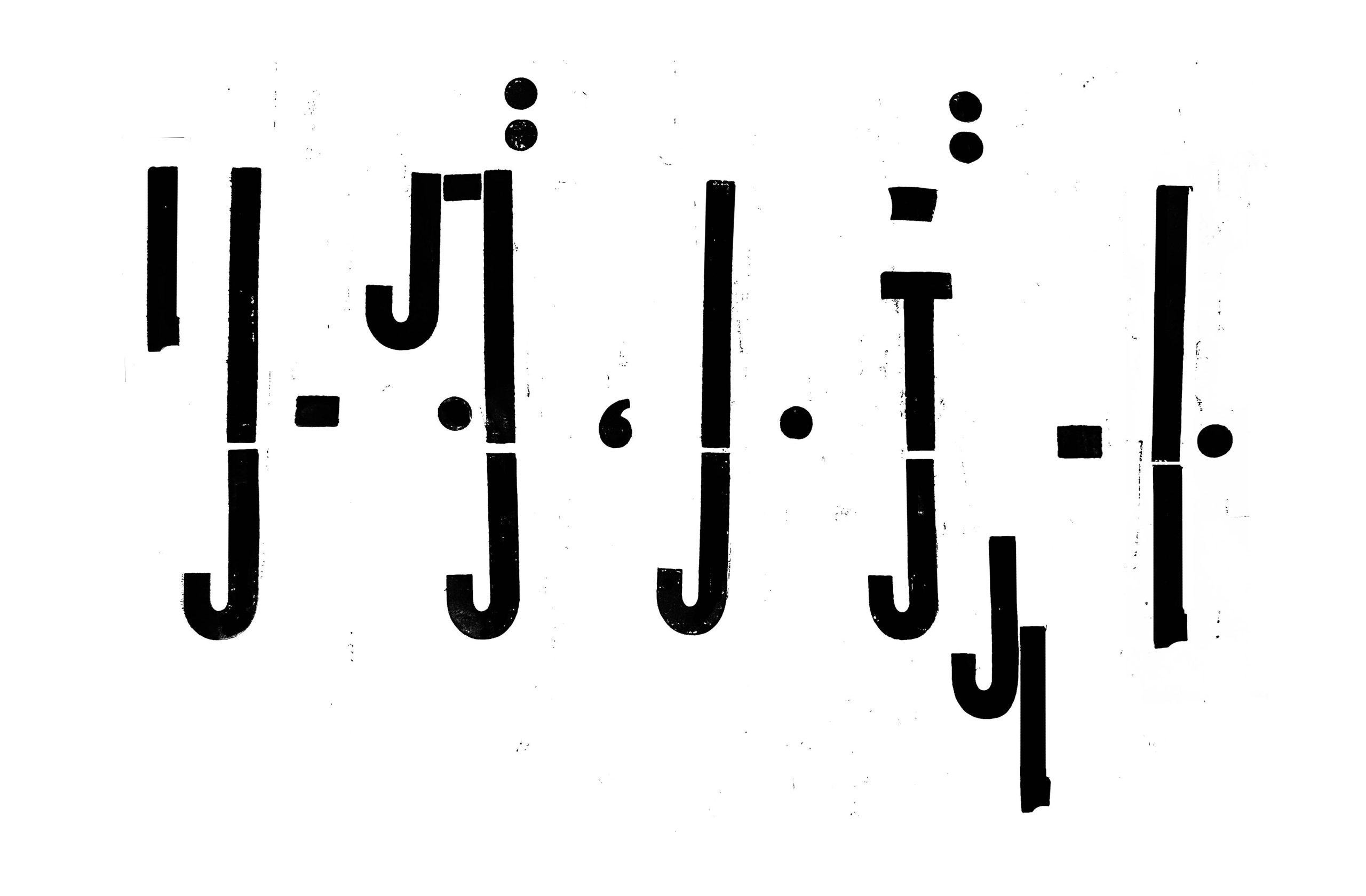THANK YOU
『わたしをひらくしごと』公開インタビュー 掲載

2019年4月21日に、『わたしをひらくしごと』著者の野村美丘さんによる、READAN DEAT店主への公開インタビューの内容が、出版元のアノニマ・スタジオwebサイトにて掲載されています。
我ながらあまりにも率直すぎる内容で関係各所にご迷惑をおかけしないかやや心配ではあります。長文で読み終わるまでに10分以上かかるのでお時間があるときに、よろしければご覧ください。
https://www.anonima-studio.com/talk-20190421/readandeat-20190421.html
本屋の雑な未来予想

とある地方都市の話。自動運転技術の法的整備が進まぬなか、配送料は値上がりし続け、取次会社が地方の書店へ厳しい条件の配送手数料を求めるようになった。書店は発注・返品回数を少なくして対応した結果、店頭からは新刊が減り、傷んだ本が目立つようになった。一方、全国チェーンの大型書店はセルフレジや高度な検索システムの導入、AIによる選書コーナーなど、売場の合理化と人件費削減を試みるが、そこで働く書店員の顔が見えなくなった結果、皮肉にも顧客離れが進む。
古書店の場合、売上確保のために欠かせないのがamazonマーケットプレイスへの出品だが、それにより古書の市場価格が透明化。また、消費者と消費者をダイレクトにつなぐフリマアプリの使用率が全世代で増加した結果、重たい本を何十冊も古書店へ持ち込み安い値段で売るよりも、アプリを使って自宅で手軽に市場価格で本を売る人が急増する。市場全体の古書流通量は減り、古書店の品揃えはおのずと希少性と専門性が求められるようになる。
だんだんと街から書店が消えていくなかで、純粋に読書を愛する「本好き」のニーズには、インフラ化したwebサービスがしっかりと応え続ける。しかし、本に囲まれた空間を愛する「本屋好き」のニーズが顕在化。その需要に応えるように、街のはずれに個人経営の小さな本屋が少しずつ増え始める。現場で経験を積んだ書店員、ダブルワークの会社員など、経歴も職種も様々だが、いずれも店主の個性が見える品揃え。本と相性の良いカフェやギャラリーやイベントスペースとしても稼働させ、本以外の収益源を確保しながら本屋を続けている。
どれだけ紙の本の素晴らしさを訴えたとしても、世の中の流れは止まらない。靴を履くようになれば草履や下駄の需要はなくなり、電気が普及すればランプは骨董品になる。娯楽や情報収集がPCやスマートフォンで満たされ、電子書籍が普及した時代に、本屋を続ける理由はなんだろうか。
その答えは「場所」だ。
「本」そのものは草履やランプと同じ「販売物」だが、それと同時に、著者や編集者やブックデザイナーなど、関わった人の思いが形になった、例えるなら「人」そのものだと思う。本屋の仕事とは、多様な「人」の声をリアルな「場所」を通して届けることだ。ネット社会が進めば進むほど、現実世界ではその「場所」でしか味わえない、リアルな体験を人は求めている。それは店主や常連と語り合うことだったり、アート作品の鑑賞やライブ演奏を楽しむことだったり、著者に会って話を聞くことだったり。カフェやギャラリーやイベントスペースには、本の魅力をリアルの「場所」で引き出す力を備えている。
街から書店がなくなる未来。これは誰かにとってのディストピアかもしれない。しかし、時代の変化に合わせながらも独自のスタイルを押し通す、しなやかに意地を張る小さな本屋たちがポツポツと灯をともし始めている。用がなくても寄りたくなるサードプレイスとして在り続けるため。人生を変えるかもしれない一冊との出会いを用意しておくため。そして自分のため。規模も品揃えも営業スタイルも違うけれど、そういう小さな店が本屋スピリッツを継いでいくと信じている。
夜をあかして

先代から店を受け継ぎ、何十年ものれんを守ってきたアケミさんも80代。一見さんはお断り。4、5回行ってようやく顔を覚えてもらったときは嬉しかった。腰が痛むんよ〜と辛そうな声で夜遅くまで営業する姿に、長年通う常連さんは心の底から心配している様子。そしてその数ヶ月後にお休みの貼り紙。またしばらくして店の前を通りがかったとき、看板が取り外されていた。もうあのカウンター席に座ることもできないんだという、しんみりした気持ち。それと同時にほっとした気持ち。アケミさん、おいしいテールスープをありがとうございました。お疲れさまでした。ゆっくり休んでください。
当たり前だけど「何を売るか」「何を企画するか」など、経営者の判断で店は成り立っていて、店は経営者のものだ。その一方、「街に在る」「街に開かれている」という意味では、個人店であっても、店はある種の公共性を持っている。そのように考えると、我が道を行く個性的な店も、その街の機能の一部であり、お客さんとその場所をカタチ作っていると言える。
多様な文化、価値観を提供することができる「本」そのものにも公共性は備わっていて、街にとって書店は欠かせない場所のひとつだと思う。しかし、この場で改めて言うまでもなく、利益率の低い書籍の売上は年々減り続け、流通コストは増える一方。そのしわ寄せは現場に及び、何かと暗い話題が多い。どの業界にも悩みはあると思うけれど、書店業界が抱える問題は険しい坂道というより断崖絶壁をよじ登っているようだ。
それでも、あえて個人で本屋の世界に飛び込む人は、強い想いを持っていて、さらに続けるための工夫や仕掛けをこらしている。それぞれの場所で、それぞれのスタイルで営まれるそんなインディペンデント書店は、勝手ながらどこか同志のように感じている。それは正統派な本屋ではないかもしれないけれど、時代に合わせた軽やかさは活き活きとしていて健康的だ。
一人ではじめた店ではあるけれど、それはもう、自分だけのものではない。そう思うと背筋が伸びる。ただ、それでもいつか店を閉める時が来る。それは弱気からではなく、最後のその瞬間までが個人店をやる意味だと思うからだ。幸い、まだ想像できないけれど、その時まで少しでも前へ進みたい。良い店にしていきたい。そのように思う5年目です。
僕とうつわ

20代半ば頃、古民家レストランに併設されたギャラリーで初めて陶器を買った。白い化粧土と黒い素地のコントラストが楽しいフリーカップ。それはこの世に一点限りの作品であり、日常の道具でもある。そのアンビバレントな魅力に惹かれた。だけどそれ以上に、沢山並んだ物の中からどうしてそれを選んだのか、自分自身で説明がつかないことに興味を覚えた。あとで調べると恩塚正二という陶芸家の物だった。それから少しづつ、理由は分からずも惹かれる物を集めていった。本屋を始めると決めたとき、もう一つの商品の柱としてうつわを扱うことを決めたのは、その答えを追い求めていきたいと思ったから。接客中に言葉で作品を伝える作業によって、なぜこれを選んだのか自分自身にも問いかけている。何事もそうだけど学ぶことでしか前へ進めない。
同じく20代半ば頃、『蟲師』というファンタジー漫画にハマった。江戸と明治の間という時代を舞台に、各地を転々と旅する主人公が不思議な現象に遭遇するという一話完結のストーリー。架空の民間伝承をベースにしていながら日本の原風景を描いているようで、それから民俗学にも興味を抱くようになった。特に、1930年代から全国に残る慣習や風俗を調査した民俗学者・宮本常一の、旅に捧げたその生き方にも憧れた。代表作『忘れられた日本人』や彼の膨大な数の著作からは、現代で忘れ去られた庶民の文化や暮らしが、たった数世代前の時代には色濃く残されていたことが分かる。世の中の流れを止めることはできないし、その必要もないけれど、一度失われた文化はそっくりそのまま取り戻すことはできない。
店を始めて間もない頃、鎌倉の民藝店・もやい工藝の久野恵一さんを人から紹介してもらい、民藝の企画展を行うようになった。大学時代に宮本常一に師事し、卒業後もやい工藝を開いた久野さんは、明るく屈託のない人柄で、全国の作り手たちと信頼関係を築いた。若い陶工への指導、現代の生活になじむ製品の提案にくわえ、箕や大壺といった時代の変化によって需要が減る物も、その制作技術を保護するために注文し続けた。すぐれた日本の手仕事を次世代につなげるために尽力した姿は、農業指導や離島振興に力を注いだ宮本常一に重なる。現在は息子・久野民樹さんが中心となり、同時代に作られる逞しく美しい手仕事の魅力を発信している。
うつわ作家の個展を企画するとき、できる限りその人自身を表現したいと思っている。作家の思考を手のひらから土や木という素材に伝え、生み出した形。表現する媒体は違うけれど、画家やイラストレーター、写真家を迎えるときと同じような感覚で向き合っている。その一方、民藝の企画展では、無私の境地から生まれる手仕事の美しさを伝えていきたいと思っている。また、自分自身、地域風土が育む工芸を通して日本の原風景に思いを馳せているのかもしれない。
作家性と無名性。在り方は違うけれど、どちらもそばに置くことで得ることができる心の豊かさは大きく、自分が良いと思う物を届けていきたい。それは多様なカルチャーを発信する本屋だから可能だと思うし、そういうオルタナティブな場所にしていきたい。つまり、一つの嗜好性を意図的に定めるではなく、どんなジャンルでも自分が強く惹かれた物は積極的に取り上げていきたい。このように書くとつくづくエゴイスティックな店だと気付かされますが、今はそのようにやっていきたいと思っています。
シャツのはなし
 私服勤務という自分への口実もあり、会社員だった頃は服を買うことが大きな楽しみだった。それは休日に街へ出かけてお金を使うというストレス発散法でもあった。転勤で東京に引っ越してからはますます加熱し、気になるブランドをWEBや雑誌でチェックして緊張しながらセレクトショップを見て回った。地方から出てきて浮き足立っていることは十分自覚しつつ買い物を楽しんでいた。
私服勤務という自分への口実もあり、会社員だった頃は服を買うことが大きな楽しみだった。それは休日に街へ出かけてお金を使うというストレス発散法でもあった。転勤で東京に引っ越してからはますます加熱し、気になるブランドをWEBや雑誌でチェックして緊張しながらセレクトショップを見て回った。地方から出てきて浮き足立っていることは十分自覚しつつ買い物を楽しんでいた。
あるとき、初めて行ったお店で一枚のシャツに心をガシっと掴まれた。飾り気がなくそっけないけど気のきいたデザイン。当時そのブランドはブレイク前夜だったこともあり「自分が見つけた!」と勝手に思い込んでしまった。直営店で新商品をチェック、欲しいものが品切れのときは別の取扱い店で通販してまで買うようになっていた。元々は一枚のそのシャツが好きだったのに、いつしかブランドのタグが重要になっていた。そのうちの何着かは数回しか着ないままクローゼットで出番を待っている。
世の中に溢れかえる商品の中から何かを選ぶとき、その背景にあるストーリーを重視することがある。社会貢献している企業への共感として商品を買うとき、情熱を持った作り手へのエールとしてお金を使うとき、単純に商品を買うときと比べて満足度が高い。
少し話は逸れるけど、目標実現のための資金をネット上で募るクラウドファウンディングで絵本を出版したいというプロジェクトをたまたま知り、強い想いに共感して少額ながら支援したことがあった。目標達成までを見守り、プロジェクト成功後に絵本が手元に届いたときは感慨もひとしおだった。
ただ、誠実に心を動かすストーリーは素晴らしいけれど、巧みに演出されたストーリーには意識的になりたいと思う。言い換えると、感情に訴えかけてくるストーリーに捉われず、商品そのものを見定める力を持ちたい。どんなメーカーがどんなコンセプトで作ったのかという情報だけで判断せず、どんな材質で、どんな工程で作られたのかという基本的な情報を用いて、冷静に、ある意味ドライに物自体と向き合いたい。
それでもたまにブランドやストーリーも何もかもすっ飛ばして心を奪われる出会いがある。今では袖が擦り切れてくたくたになってなお愛着が増す最初のシャツがそうだった。その出会いを見過ごさないためにできることは、調べて出かけて身銭を切って向き合って勉強すること。そう思えば東京での散財にも言い訳がつく、そんな気がします。