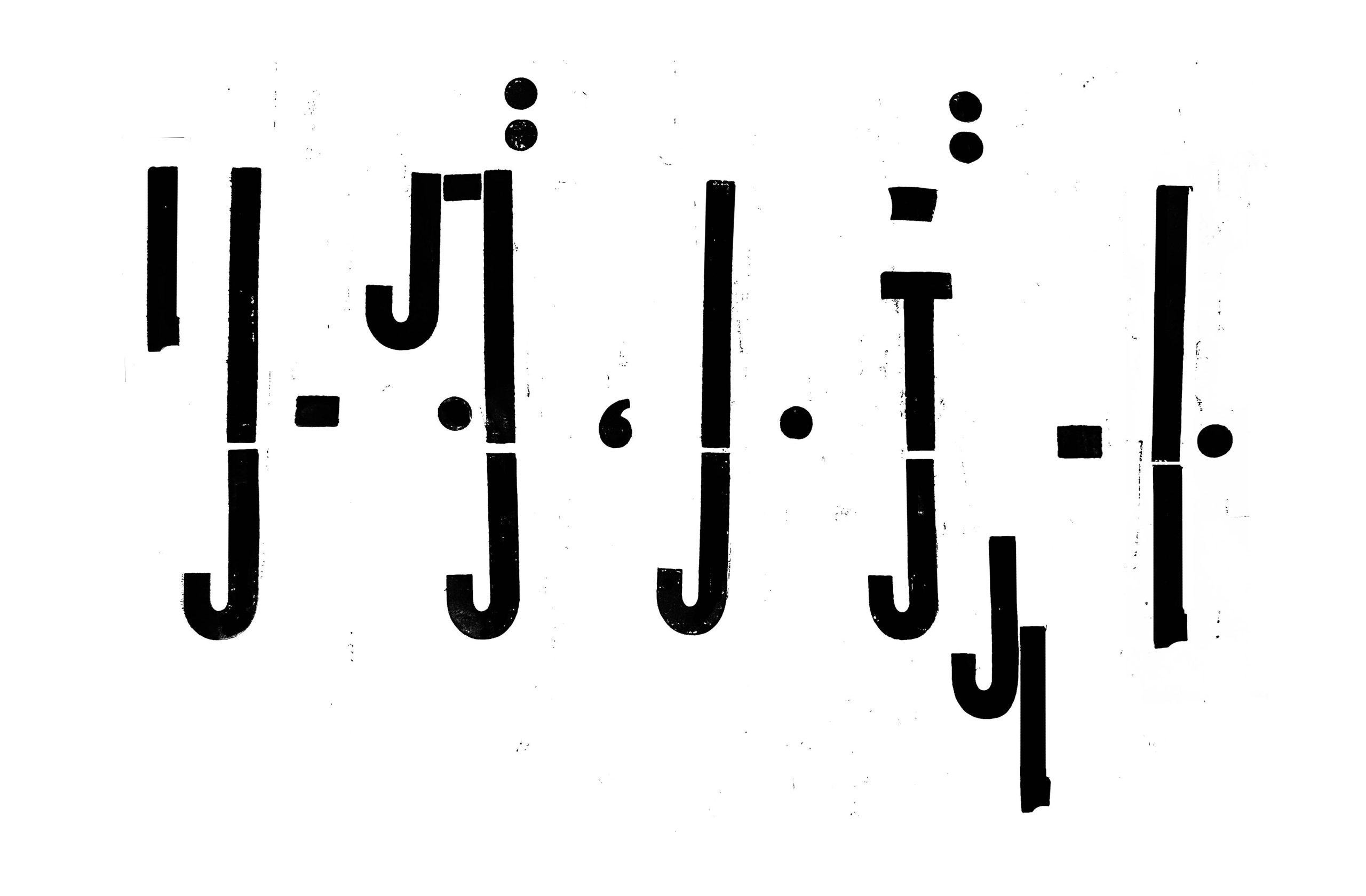Author Archive
加藤かずみ個展「glaze」


陶磁器を彩る釉薬、その色彩は化学反応によってもたらされ、パレットの上で絵の具を混ぜ合わせるように… という訳にはいきません。くすんだ乳白色や鈍く光る錆色。加藤かずみさんの器は、使い込まれたアンティークのようであり、一点ごとに異なる表情は見ごたえがあります。
淡いグラデーション。繊細なマチエール。それは作家の試行錯誤とインスピレーションの賜物。真白な磁器のキャンバスを彩る、誰にも真似できないglazeをご覧ください。
会期:12/7(土)〜 12/15(日)会期中無休 初日作家在廊
12/7(土)神泡ビアカップでビールの試飲会
お客さんの一言で気づいたという、きめ細やかな泡を生み出す加藤さんのマット釉でビアカップを作ってもらいました。初日の17時から19時、そのビアカップを使って生ビールを楽しんでもらう試飲会を企画しました。加藤さんおすすめの燻製やソーセージ、段原のベーカリー Besoin(ブズワン)のバゲットなどをおつまみに神泡で乾杯しましょう。
時間:17:00〜19:00(ビールがなくなり次第終了)
参加費:無料(ビールは二杯目以降から有料となります)
ブーメランを投げてでも

ずらり並んだ器の中からどうしてそれに惹かれたのか自分自身でもよく分からない。作家の名前も分からずに初めて買った陶のフリーカップ。その理由を求めて、全国のギャラリーのWEBサイトをチェックしたり、店に足を運んだり、いわゆる作家物の器を追いかけるようになった20代後半。それらは当時まだ名付けされていなかった「生活工芸」の器だった。
生活工芸とは何か。新潮社刊行の『工芸批評』『工芸青花 7号』を参照にしながらざっくりまとめると、高額で権威的な一点物である「鑑賞工芸」に対して、リーズナブルで定番商品として買い足すことができるシンプルな作家の器を「生活工芸」と呼ぶようになった。発信力のある数名の作家が自らカテゴライズした生活工芸、そのキーワードは丁寧な暮らし。2000年代に次々と創刊された暮らし系雑誌が後押しする形で、これまで男性が主体となって論じてきた鑑賞工芸とは全く別の、保守的なイメージから解放された、ナチュラルなライフスタイルに馴染むセンスの良い工芸、それが生活工芸だ。
『工芸批評』は、その生活工芸のフィールドにあえて批評を持ち込もうという試みだ。うんちくの世界からせっかく解放された工芸にどうして批評が必要なのか。それは裾野を広げたその先で繰り広げられる出来事に、飽き飽きと、そして辟易させられている人たちが少なからずいるからではないだろうか。
「あの人が雑誌で紹介したあの作家の器が欲しい!」手仕事の希少性は購買欲を刺激する。知識よりも感性が重視され、買いやすい価格帯の生活工芸は、鑑賞工芸と比べるまでもなく商品として扱いやすい。消費者の求めに応じるように、それらを取り扱う店やギャラリーは増え、その結果、新たに作家デビューする人も増えていく。
マーケットが拡がり、選択肢が増えることは喜ばしいことだけど、なぜかもやもやと不健全な空気が漂っている。なぜなら、買い手も売り手も、自分自身の「眼」を持とうとせず、付加情報ばかりに気を配っているからだ。「消費」することが目的なので、物を見ているようで見ていない。その一方で失敗したくないという心理が働き、目利きと呼ばれる他人の眼を頼る。
SNSの登場はさらに事態を加速させる。人気作家のタグが付いた、いいね待ちの投稿が世の中に溢れ、承認欲求の道具として次々と消費されている。またSNSは作家にも影響を及ぼしかねない。流行を模倣し、あえて消費されることを目指す作り手が出てくる可能性もあるだろう。クリエイティブには必然的に孤独がつきまとう。自分と対峙したその先にようやく掴むものだと思う。
生活工芸がもたらしたのは、工芸の大衆化だ。勿論そのなかには自分の眼を持った使い手も、自分の道を歩む作家もたくさんいるが、上記の推測もあながち突飛ではないと思う。だからこそ、ちゃんと物を見ようという啓蒙活動が必要であり、求められているのだと思う。物を見るときに言葉を持つということは、眼を持つことにも繋がっていく。
「ちゃんと物を見よう。」と投げかけたこの言葉は、冒頭に登場する自分自身に対してブーメランのように鋭く返ってくる。なぜそれが良いのか。どうして店で扱うのか。言語化するということは、頭の中のぼんやりとした思考を定義化し、アウトプットすることだ。感覚的に惹かれた世界を思考し、言葉で読み解いたその先に、自分の眼に辿り着く。それは「消費」以上に刺激的だ。
11月のお休み

11月のスケジュールは変則的なお休みとなっておりますのでご注意ください。
火曜定休 + 臨時休業:11/9(土)、11/10(日)、12/6(金)
11/2(土)〜4(月・祝)
川央ヒロコ個展「silent jog」
イラストレーター・川央ヒロコさんの個展「silent jog」を開催します。ドローイングを中心とした作品が並びます。
http://readan-deat.com/blog/2019/10/21/sj/
11/16(土)〜12/1(日)
弁造さんのエスキース展 -今日も完成しない絵を描いて-
生前いつか個展を開いてみたいと語っていた弁造さんの想いに、写真家・奥山淳志が応えた展覧会。初日はトークイベントも開催。
http://readan-deat.com/blog/2019/10/21/benzo/」
11/20(水)〜12/8(日)
『ガンツウ|guntû』(millegraph)刊行記念 鈴木研一の写真+堀部安嗣のドローイング展
瀬戸内海に就航した客船 ガンツウの魅力が詰まった展覧会。初日はトークイベントも開催します。会場は当店から徒歩3分ほどのギャラリー「A not B」です。
http://readan-deat.com/blog/2019/10/17/guntu/
また、12/7(土)〜15(日)は、陶芸家・加藤かずみさんの個展を開催します。「glaze」(=釉薬)をテーマに、独自の色合いを追求する加藤さんの作品をご紹介します。
弁造さんのエスキース展




北海道の丸太小屋で自給自足の生活を営み、糧を生みだす庭と暮らす「弁造さん」の姿を14年にわたって撮影し続けた写真家・奥山淳志さん。弁造さんの物語をまとめた心揺さぶる写文集『庭とエスキース』(みすず書房)をこの春に刊行されました。
自力で掘った池、「自給自足は楽しくなければならない」と植えた果樹や野菜、風景に季節の色彩をもたらす木々や草花に彩られた、豊かな庭。弁造さんと弁造さんの庭に心を奪われた奥山さんは、その丸太小屋を訪ねるうちに、小屋の中央に置かれたイーゼルに向かう弁造さんのもう一つの姿を知ります。
今回の展覧会では、弁造さんが描き遺したエスキース(=作品を制作する上で構想などを描きとめた下描き)を展示します。初日11/16(土)は、奥山さんのトークイベントを開催します。
生涯、独身だった弁造さんはなぜ庭に木を植え続けたのか、そしてなぜ女性たちの絵を描き続けたのか。弁造さんの「生きること」を想い、誠実な眼差しで向き合った奥山さんの言葉に、ぜひ耳を傾けてみてください。






いつまでも完成しない絵を描き続ける。僕が弁造さんを見つめたのは、1998年から2012年までの14年間でしたが、弁造さんという人はいつもそうでした。ひと部屋しかない小さな丸太小屋のなかでイーゼルに向き合い、女性をモチーフにした“エスキース”ばかりを描き続けました。南国を思わせる木陰で横たわる裸の女性。自慢の髪をかきあげる女性。何気ないひとときを過ごす母と娘。北海道で畑と森からなる「庭」を作って自給自足の生活を続け、生涯を独身で過ごした弁造さんがなぜこのような縁もゆかりもない女性たちを描き続けたのか。それは僕にとって、“弁造さん”を知るうえで欠かすことができない問いかけでした。
しかし、弁造さんは女性たちを描く理由を語らぬまま、92歳の春にプイと逝ってしまいました。でも、だからなのでしょう。弁造さんが逝ってしまって7年の月日が流れた今日であっても、僕は新たな想像を抱くことを許されます。鮮やかな向日葵色をまとった女性たちのおしゃべりに耳を傾け、弁造さんの胸の内を思い描き、そのたびに新たな弁造さんから“生きること”の奥深さを見つけるのです。
弁造さんがいなくなってしまった丸太小屋にはたくさんのエスキースが遺されていました。その一枚一枚に描かれた筆跡を辿りながら、弁造さんの“生きること”から放たれている光の綾を一緒に感じていただけますように。
写真家 奥山淳志

井上弁造(1920-2012)
大正9年 北海道総富地(そっち)に生まれ、数え年7歳で総富地尋常小学校に入学。16歳で中徳富(なかとっぷ)高等小学校を卒業。その後は家事を手伝う。父は農産物検査員の傍ら小作農を営む。19歳の春に現在地(当時は作り枯らしの荒地)に入植。自分は夏、農業の手伝い、冬は叔母の家のある東京で洋画を学ぶ。戦中、兄と弟が兵役、自分は2ヶ月の教育招集で家を守って終戦を迎える。戦後は出稼ぎや日雇いと忙しく絵を描く時間も少なく70歳で体調を崩す。今88歳、もし一度個展をひらくことが出来たら幸いです」(2009年、当時88歳の弁造さんが自らの略歴を記す)

奥山淳志(おくやま・あつし)
1972年大阪生まれ,奈良県育ち.京都外国語大学卒業後,出版社に勤務. 1998年岩手県雫石町に移住し,写真家として活動を開始.以後,東北の風土や文化を撮影するほか, 人間の生きることをテーマにした作品制作をおこなう. 受賞歴に2006年「Country Songs ここで生きている」でフォトドキュメンタリーNIPPON2006,2015年「あたらしい糸に」で第40回伊奈信男賞,写真集『弁造 Benzo』および個展「庭とエスキース」(ニコンサロン)で2018年日本写真家協会新人賞, 2019年第35回 写真の町 東川賞・特別作家賞がある。2019年『庭とエスキース』(みすず書房)を上梓。
弁造さんのエスキース展 -今日も完成しない絵を描いて-
会期:11/16(土)〜12/1(日)
奥山淳志トーク&スライドショー
日時:11/16(土) 18:00〜19:30(受付17:30〜)
料金:1,000円
定員:30名
会場: READAN DEAT
【お申込み方法】
以下のコンタクトフォームに題名を「奥山さんトークイベント」として、メッセージ本文に
1. お名前 2. 参加人数 3. 電話番号 をご記入の上お申し込みください。
また、お電話(082-961-4545)でも受付けております。
コンタクトフォームから送信できない場合、上記と同じ項目を以下のメールアドレスにお送りください。
info☆readan-deat.com ☆は@に置き換えてください。
川央ヒロコ個展「silent jog」

東京在住のイラストレーター・川央ヒロコさんの個展を開催します。ドローイングを中心とした展覧会です。
日々撮りためている気になった風景。その写真の中から、どこにでもある、もしくはどこにも無かったかもしれない風景を描きました。どうせなら気分の上がるものを。過去に制作した作品も、いくつか展示する予定です。合わせて楽しんでいただけますと幸いです。
川央ヒロコ|Hiroko Kawanaka
1981年生まれ。東京都在住。セツ・モードセミナーを卒業。第201回、第208回ザ・チョイス入選。都内を中心に活動中。
https://hrk-kawanaka.com
会期:11/2(土)〜11/4(月)